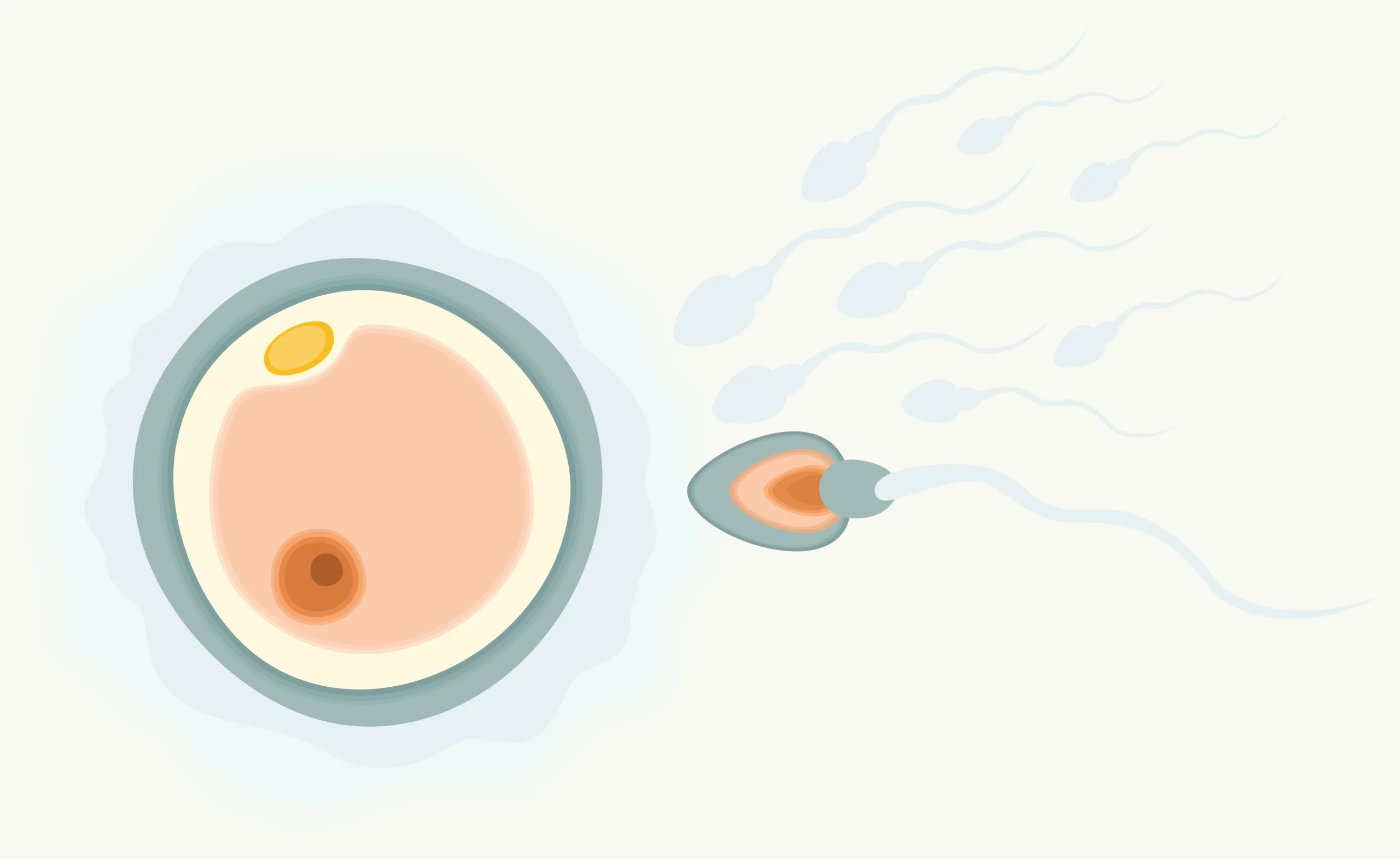執筆者兼監修者プロフィール
東大産婦人科に入局後、長野県立こども病院、虎の門病院、関東労災病院、東京警察病院、東京都立豊島病院、東大病院など複数の病院勤務を経てレディースクリニックなみなみ院長に就任。
資格
- 医学博士
- 日本産科婦人科学会 産婦人科専門医
- FMF認定超音波医
…続きを見る
排卵検査薬の使い方、陽性・陰性の見方を解説。陽性が出た時の最適なタイミングはいつ?薄い線が続く、陽性にならない原因や、妊娠しない場合に病院へ相談する目安も紹介。妊活中の疑問に答えます。
妊活を始めて排卵検査薬を使い始めたものの、「排卵検査薬って本当に合っているの?」「陽性になったけど、いつタイミングを取ればいいの?」「ずっと薄い線しか出ないけど大丈夫?」と不安になる方も多いのではないでしょうか。初めてのことで戸惑いや疑問を感じるのは自然なことですね。
結論から言うと、排卵検査薬は排卵直前のホルモン変化(LHサージ)を捉えることで妊娠の可能性を高める心強いツールです。 正しく使えばタイミング法の成功率アップに役立ちますが、その一方で使い方や結果の解釈に迷うこともありますよね。そこで本記事では、排卵検査薬の仕組みや正しい使い方、陽性・陰性の見方や最適なタイミングの取り方はもちろん、うまく結果が出ない場合の原因や注意点、基礎体温との違い、さらに妊娠に至らないときにクリニックでできることまで詳しく解説します。
この記事を読むことで次のような疑問に答えます:
- 排卵検査薬はどんな仕組みで妊活に有効なの?基礎体温法との違いは?
- 排卵検査薬はいつから使い始め、どのように検査するのが正しいの?
- 「陽性」「陰性」の判定ラインの見分け方と、陽性が出たらいつタイミングを取ればいい?
- 排卵検査薬で陽性にならない、または薄い線ばかりで濃くならない場合はどうすればいい?
- 検査薬を使っているのになかなか妊娠しない場合、どのタイミングで病院に相談すべき?
不安や疑問に寄り添いながら、妊娠の可能性を高めるための正しい排卵検査薬の活用方法を一緒に見ていきましょう。
「排卵検査薬」とは?妊娠の可能性を高める仕組み
排卵検査薬とは、尿中のLH(黄体形成ホルモン)濃度を測定することで排卵日を予測する検査薬です。排卵の約24~36時間前になるとLHが急激に増加し(これを「LHサージ」と呼びます)、その変化を捉えることで「もうすぐ排卵が起こるサイン」を知ることができます。タイミングよく性交の機会を持てるため、妊娠の可能性を高めるのに役立つ仕組みです。
仕組み:排卵のサイン「LHサージ」を検出します
女性の体では月経周期の中頃にLHホルモンが急上昇するLHサージという現象が起こり、このLHサージが引き金となって排卵が起こります。排卵検査薬は尿中のLH濃度が一定以上になると反応し、ラインの濃さやデジタル表示でLHサージの発生を知らせます。LHは普段から少量ずつ分泌されていますが、排卵前だけ一時的に大量に分泌されるため、この急上昇を検査薬で捉えることで「今まさに排卵直前である」ことを知ることができます。言い換えれば、排卵検査薬の陽性反応は「排卵の予兆をとらえたサイン」なのです。
排卵検査薬を使うメリットとは?
排卵検査薬を活用する最大のメリットは、妊娠しやすいタイミングを事前に把握できることです。カレンダーによる排卵日の予測や体調の勘頼りではなく、ホルモン値の変化という客観的な指標で排卵の直前を知ることができます。排卵日はストレスや体調で前後することもありますが、LHサージの検出によってタイミングを逃しにくくなるでしょう。結果として、自己流でタイミングを取るよりも妊娠率の向上が期待できます。
また、排卵検査薬は自宅で手軽に行える点も利点です。従来は排卵の兆候を知るには基礎体温の継続測定や病院での血液検査が必要でしたが、市販の検査薬を使えば自分のペースでチェックできます。特に仕事や育児で忙しい方でも、検査薬を使えば短時間で結果がわかるため負担が少ないでしょう。結果が目に見える形で出ることで安心感が得られる方もいます。
もっとも、排卵検査薬は妊娠を保証するものではない点には注意が必要です。卵子と精子が出会うタイミングを最適化するサポートにはなりますが、妊娠の成立には精子・卵子の質やその他の要因も関わります。それでも、適切に活用することで妊活の効率を高められる有用なツールであることは間違いありません。
基礎体温との違いと、併用するメリット
排卵日の予測手段としては、排卵検査薬のほかに基礎体温法もよく用いられます。それぞれの特徴の違いを下の表にまとめました。両者を正しく理解し、状況に応じて併用するとより確実にご自身の排卵パターンを把握できます。
| 基礎体温法 | 排卵検査薬 | |
|---|---|---|
| 分かること | 排卵が起こったかどうか(過去の排卵の有無) | 排卵が近いかどうか(未来の排卵予測) |
| タイミング | 毎朝、起床前に体温を測り記録。排卵後に体温上昇(高温期入り)を確認 | 次の生理予定日の17日前から検査開始。以降、毎日ほぼ同じ時間帯に尿検査を実施 |
| メリット | ホルモン変化による体調リズムがわかる。高温期の長さで黄体機能の目安も把握できる | 排卵の予測精度が高く、妊娠しやすい「排卵直前」のタイミングを逃さず捉えられる |
| デメリット | 継続的な測定習慣が必要。起床後すぐに把握しなければ正確に測定できない | 検査薬の購入費用がかかる。周期が乱れていると長期間検査が必要になる場合もある |
| 備考 | 無排卵周期の発見に役立つ。 | LHサージが起きても稀に排卵しない場合があるため(後述)、基礎体温も併用して高温期入りを確認するのがおすすめ |
基礎体温法は過去の排卵を確認する方法であり、排卵検査薬はこれから起こる排卵を予測する方法です。それぞれ単体でも妊活に有用ですが、併用することで「排卵の予測」と「実際に排卵したかの確認」の両方が可能になります。例えば排卵検査薬で陽性が出てタイミングを取った後、その後に基礎体温で高温期へ移行すれば「無事に排卵が起きた」とわかり安心できます。逆に基礎体温が高温期にならなければ、検査薬は陽性でも排卵しなかった可能性が考えられるため、早めに医師に相談する判断材料にもなるのです。
排卵検査薬はいつから使い始める?
排卵検査薬を効果的に使うには、適切なタイミングで使い始めることが大切です。焦って早すぎる時期から始めたり、逆に遅すぎてLHサージを見逃したりしないよう、まずは以下のポイントを押さえましょう。
まずはご自身の「月経周期(生理周期)」を知りましょう
排卵検査薬の使用開始時期は、人それぞれの月経周期の長さによって変わります。まずはご自身の月経周期を把握しましょう。月経周期とは、生理開始日(出血が始まった日)を1日目として、次の生理が来る前日までの日数のことです。一般的な周期は25~38日と言われますが、個人差があります。過去数ヶ月の生理開始日をカレンダーやアプリで記録し、自分は平均何日周期かを確認してみてください。周期が毎回ほぼ一定の方もいれば、月によってばらつきがある方もいます。
もし月経不順で周期が読みにくい場合は、検査薬を使用する前に一度婦人科で相談することをおすすめします。周期が極端に不規則だと自分で検査開始日を決めにくく、長期間にわたって検査薬を使い続ける必要が出てしまうためです。医師と相談すれば、排卵誘発剤の使用や定期的な卵胞チェックなど適切な対応策を提案してもらえるでしょう。
使い始める日の目安(計算方法)
排卵検査薬は、一般に「次の生理予定日の約17日前」から使い始めるのが目安です。これは、多くの製品の添付文書にも記載されている計算法です。17日前というのは、排卵が生理予定日の14日前頃に起こるケースが多いため、安全策としてさらに数日前(3日前)から余裕をもって検査を開始するという考え方になります。
例えば、周期が28日で安定している方の場合:次の生理予定日の17日前は周期11日目にあたります(28-17=11)。生理開始日を1日目と数えて11日目から検査開始です。同様に、周期30日なら13日目、周期25日なら8日目あたりから始めます。ご自身の平均周期に当てはめて計算し、カレンダーや手帳に「排卵検査開始日」をチェックしておきましょう。
なお、過去数周期で長さにばらつきがある場合は、最も短かった周期に合わせて開始日を計算する方が安心です。たとえば前回は32日周期だったけど短い時は26日周期になることも…という方は、26日周期基準で開始日を設定したほうがLHサージを見逃しにくくなります。逆に予定より早く検査を始めてしまっても大きな問題はありません(多少キットを余分に消費する程度)が、遅れて開始すると排卵を逃してしまう可能性があるため注意しましょう。
1日何回?いつの尿で検査するのがベスト?
基本的には1日1回の検査で十分ですが、検査する時間帯にはコツがあります。排卵検査薬はいつ測定しても構いませんが、LHサージを確実に捉えるためには毎日なるべく同じ時間帯に行うと良いでしょう。おすすめは午後~夜(例えばお昼12時~夜10時頃まで)の間です。LHサージは朝に始まることが多く、始まってすぐの数時間は尿中濃度が十分上がらず検出できない場合があります。そのため、朝早い時間よりは日中~夕方以降の尿で検査した方が陽性を捉えやすいのです。実際、「午後4時~10時頃に検査するのが良い」という報告もあります。
また、検査前には過剰な水分摂取を避けるようにしましょう。水分を摂りすぎると尿が薄まり、LH濃度も相対的に薄くなって検査薬の反応が弱くなってしまいます。検査の2時間前くらいからお茶や水をがぶがぶ飲むのは控え、どうしても喉が渇いたときは一口二口にとどめておくと安心です。
なお、市販の排卵検査薬では「朝一番の尿で検査しないでください」と注意書きされているものもあります。朝一の尿は一晩かけて濃縮されているためLH濃度も高めに出やすく、まだLHサージが始まっていないのに誤って陽性に見えてしまう(偽陽性)のリスクがあるためです。特別な理由がなければ朝起きてすぐの尿は避け、2回目以降の尿で検査すると良いでしょう。どうしても生活パターン的に朝しか時間が取れない場合は、その時間帯で毎日検査して構いませんが、検査直前の水分量など条件をなるべく一定にするよう心がけてください。
排卵検査薬の正しい使い方【5つのステップ】
ここからは、排卵検査薬の基本的な使い方を5つのステップに沿って説明します。初めて使う方でも迷わず実践できるよう、準備から検査・判定・タイミングの取り方まで順番に見ていきましょう。
ステップ1:準備(検査のタイミングと注意点)
まずは検査を始める日と時間帯を決め、必要な物を準備します。先述のとおり、検査開始日は生理周期に合わせて設定しましょう。例えば「生理開始から◯日目から始める」と決めたら、その日になったら忘れず検査を始めます。また、開始日より前に検査薬キットを必要な本数だけ用意しておきましょう。ドラッグストアや通販で購入できますが、第1類医薬品のため薬剤師の説明が必要です。日数に余裕をもって入手してくださいね。
検査する時間帯もこの段階で決めておくと安心です。毎日忙しい場合は「夜○時にお風呂に入る前に検査」など自分の生活リズムに組み込む形で習慣化すると良いでしょう。検査直前の注意としては、尿が薄まりすぎないよう1~2時間ほど前から水分は控えめにします。トイレも直前に済ませてしまうと検査用の尿が出なくなるので、なるべく検査時刻まで我慢した方が確実です。
ステップ2:採尿・検査
準備が整ったら、実際に尿を採取して検査薬を使用します。具体的な手順は製品によって多少異なりますが、一般的には次のような流れです。
- キットを開封する – 個包装になっている検査スティック(または試験紙)を取り出します。使う直前まで開封しないようにし、また有効期限が過ぎていないか確認しましょう。
- 採尿部分に尿をかける or つける – スティック型の場合は先端の採尿部に数秒間直接尿をかけます。試験紙型の場合は清潔な容器にとった尿に先端を浸します(浸す時間は説明書記載通りに)。このとき、決められた以上の時間浸けすぎないよう注意が必要です。
- 水平な場所に置いて待つ – 尿をかけ終わったらキャップを閉め、キットを平らな所に置いて指定の時間(おおむね5分前後)待ちます。すぐに結果窓を覗かず、説明書に書かれた判定時間が経過するまで動かさず放置してください。
以上で検査自体は完了です。難しい操作は特になく、妊娠検査薬と使い方はほとんど同じです。必ず各製品の説明書に従い、適切な手順で行ってくださいね。もし尿をかけすぎてしまった・逆に不足したかも…など手順ミスが起きた場合は、そのスティックの結果は当てにならない可能性があります。その際は新しい検査薬でもう一度やり直しましょう。
ステップ3:判定(陽性・陰性の見方)
指定の時間待ったら、いよいよ結果を判定窓のラインで確認します。判定の基本はシンプルで、「線の濃さ」を見るだけです。ただし初めてだと基準が分からず迷うこともあるので、ここで陽性・陰性それぞれの目安を説明します。
「陽性(強陽性)」とは?
排卵検査薬における「陽性」とは、判定ライン(テストライン)の濃さが基準ライン(コントロールライン)と同じか、それ以上に濃く出た状態を指します。基準ラインは検査が正常に行われたことを示す線で、必ず表示される対照線です。それに比べてテストラインがはっきりと濃く現れていれば、尿中LH濃度が高まっている=LHサージが起きていると判断できます。メーカーによっては「判定線が基準線より濃い場合を特に“強陽性”と呼ぶ」と説明しているものもありますが、一般的には基準線と同程度以上の濃さなら排卵直前の陽性反応と考えて問題ありません。
デジタル表示タイプの排卵検査薬の場合は、笑顔マークや特定の記号で陽性を知らせてくれるので、ラインの濃淡に悩む必要はありません。一方、ライン表示タイプでは光の加減や個人の主観で判定が分かれるケースもあります。明らかな陽性は判定に迷うことは少ないですが、「基準線より少し薄いかな?同じくらいかな?」と微妙な時もあるでしょう。判定に迷うときは翌日も同じ時間に検査を続けてみてください。翌日により濃い陽性が出れば前日はまだ陰性寄りだったとわかりますし、逆に翌日に薄くなったなら前日がピークだったと推測できます。陽性が出たと思ったら、その日からタイミングをとるようにしましょう(タイミングの詳細は後述)。
「陰性」とは?
「陰性」は陽性の基準を満たさない結果のことです。判定ラインが全く現れないか、出ても基準ラインより明らかに薄い場合は陰性と判断します。多くの検査薬では薄い線しか出ない場合も「陰性」扱いです。したがって、たとえ判定ラインがうっすら見えても基準線と比較してかなり薄ければ、それはまだLHサージ前の陰性反応ということになります。
陰性の場合はタイミングを急ぐ必要はありません。検査を継続し、翌日以降も同じ時間に測ってみましょう。なお、基準ライン自体が出ていない場合は検査そのものが正しく行われなかった可能性があります。尿量が不足したり過剰だったりすると起こり得ますので、その際は新しいスティックでもう一度検査し直してください。連日陰性が続いているうちは排卵はまだ先と考えられますが、タイミング法をとる場合は念のため陰性の期間中も2~3日に一度程度のペースで夫婦生活を持っておくと安心です(精子は数日生存できるため、早めにスタンバイさせるイメージです)。
「うっすら陽性」が続く時はどう考えたらいい?
判定ラインが毎日うっすら出ているものの、基準線より薄い状態が何日も続いて「濃い陽性にならない」ケースもあります。いわゆる「ずっと薄い線状態」で、これを本人は「うっすら陽性が何日も続いている…」と感じて不安になることがあります。この現象の考え方ですが、基本的に薄い線は陽性ではなく陰性扱いです。LHホルモンは排卵期以外でも少量は常に分泌されているため、感度の高い検査薬だと陰性の時期でも薄い反応が出ることがあります。しかし重要なのは「濃くなったかどうか」です。薄いまま濃度が上がらないのであればLHサージは起きていない可能性が高く、つまりまだ排卵が起こっていないか、あるいは今周期は排卵しないかのどちらかです。後者の場合については、次章の「判定に迷う時・注意点」で詳しく触れます。
いずれにせよ、毎日検査しても基準線レベルの濃さにならないうちは「陽性ではない=排卵直前ではない」と判断します。焦らず検査を続けつつ、もし心配であれば基礎体温も記録して様子を見ましょう。基礎体温が低温のままなら排卵未発効ですし、一方で体温上昇があれば検査薬では捉えきれないまま排卵してしまった可能性も考えられます。そのような場合は一度婦人科で相談してみても良いでしょう。
ステップ4:結果を記録する
検査結果が出たら、その都度記録を残すことをおすすめします。特に何日目に陽性反応が出たかは妊活計画において重要な情報です。記録の方法は、ご自身が見返しやすいやり方で構いません。例えば…
- スマホで写真を撮る:判定窓を撮影しておけば、ラインの濃さを後から客観的に比較できます。日付もメモしておきましょう。
- 専用アプリに入力する:生理日管理アプリ等には排卵検査薬の結果を記録できるものもあります。「陰性」「陽性」など選択肢を選ぶだけで簡単に蓄積できます。
- 手帳やノートに書く:シンプルに「○月○日:陰性(判定線ほぼ見えず)」「○月○日:陽性(判定線=基準線くらいの濃さ)」といった具合に書き留めます。
記録をつけておくと、自分の排卵周期や傾向が見えてくるメリットがあります。例えば「毎回生理から12~13日目に陽性になるな」「このところ陽性が出るのが遅れている」などパターンを把握できるでしょう。また病院を受診する際にも、記録があると医師に状況を説明しやすくなります。少し手間かもしれませんが、未来の自分のために結果はしっかり残しておきましょう。
ステップ5:タイミングを取る
排卵検査薬で陽性反応が確認できたら、いよいよ妊娠に向けたタイミング(性交渉)を持つ段階です。陽性が出た当日から翌日にかけてが最も妊娠確率が高いタイミングとなります。できれば陽性が判明したその日のうちにパートナーと相談して性交渉の機会を持ってください。加えて翌日もチャンスがありますので、可能であれば2日連続でタイミングを取ることをおすすめします。
「連日は難しい…」という場合でも、最低どちらか1日はタイミングを持つようにしましょう。一般的に、排卵はLHサージ開始から約24~36時間以内に起こると言われています。そのため検査薬が陽性を示したということは、約1日後くらいまでに排卵する可能性が高い状況です。精子は女性の体内で48~72時間は生存できますから、陽性当日にタイミングをとっておけば精子が卵子を待ち受ける形になり理想的です。もちろん翌日でも十分間に合いますので、ご夫婦の都合に合わせてできる範囲で計画しましょう。
陽性が出たら、いつタイミングを取る?
排卵検査薬で陽性反応が確認できたとき、「さて、具体的にいつ行為を持つのがベストなの?」という疑問が出てきますよね。ここでは陽性反応と排卵までの時間差、そして最も妊娠しやすい「ゴールデンタイム」について解説します。適切なタイミングの取り方を知って、チャンスを逃さないようにしましょう。
「陽性」は「排卵直前」のサイン
まず押さえておきたいのは、排卵検査薬の陽性=排卵した、ではなく「排卵目前」であるということです。勘違いされやすいポイントですが、陽性反応が出た段階ではまだ卵子は放出されておらず、まさに排卵が起ころうとしている時期です。言い換えれば、「これから24時間以内くらいに排卵しそうですよ」というサインが陽性反応なのです。したがって、陽性を見たからといって「もう排卵しちゃったんだ!」と焦る必要はありません。しかし時間はそれほどたっぷりあるわけではないので、「今から準備すれば間に合う!」という前向きな気持ちでタイミングを取り始めましょう。
陽性(LHサージのピーク)から排卵までの時間
個人差はありますが、一般的にLHサージの開始から約24~36時間後に排卵が起こるとされています。また、LHサージの濃度が最大になった「ピーク時」から数えると10~12時間後に排卵するとも言われます。排卵検査薬は尿中LHが一定濃度に達した時点で陽性になりますので、その陽性が出たタイミングはちょうどLHサージのピーク付近または少し前と考えられます。そこから逆算すると、陽性反応が出てからおよそ半日~1日程度で実際の排卵が起こる計算です。
ただし、この時間幅には個人差や周期差があります。例えばある周期では陽性当日の夜に排卵したけれど、別の周期では陽性から2日後近くになって排卵した…というケースも報告されています。また体調やストレスによってLHサージが伸びたり弱まったりすることもあります。そのため「陽性から◯時間後に絶対排卵」と厳密に考えるよりは、陽性が出てから1~2日は排卵の可能性が高い期間と捉えておくと良いでしょう。後述しますが、その間はできるだけ複数回タイミングを持つことで妊娠のチャンスを最大化できます。
最も妊娠しやすい「ゴールデンタイム」はいつ?
人間が妊娠可能な期間は意外と短く、排卵日の前後数日間に限られています。中でも特に妊娠率が高くなるのは、一般に「排卵日の前日と当日」と言われます。これを妊活ではしばしば「ゴールデンタイム」と呼んだりします。卵子の寿命は排卵後約24時間と短い一方で、精子は射精後約2~3日間生存できるため、理論上は「排卵の少し前に精子がスタンバイしている状態」が最も受精成立しやすいのです。排卵日の前日にタイミングを取っておけば、翌日の排卵時に新鮮な精子が卵管内で待ち構えている理想的な状況になります。
以上を踏まえ、排卵検査薬で陽性が出た場合の具体的なタイミング法は次のようになります。陽性が確認できた当日とその翌日はできるだけ続けて性交渉を持ちましょう。例えば夜に陽性を知ったらその夜に1回、そして翌日ももう1回というイメージです。もし可能であれば翌々日(陽性から2日後)にも1回タイミングを持てると万全です。実際には各ご家庭の事情や体力もありますので無理のない範囲で構いませんが、「陽性当日~翌日にかけて集中してタイミングを取る」のが基本と覚えておいてください。
なお、「陽性の日以前にタイミングを取っておく」ことも有効です。LHサージは始まる前から徐々にLH濃度が上がり始めています。検査薬で陰性だった日でも、タイミングを2~3日に1回ほど持っていれば精子が常に準備された状態を維持できます。特に排卵が近づくと子宮頸管粘液(卵の白身のようなのびるおりもの)が増える自覚がある方は、その粘液が増え始めた段階でタイミングを取っておくのも良いでしょう。粘液の増加は排卵が近いサインのひとつで、いわば体が教えてくれる自然の排卵予測です。排卵検査薬の結果と合わせて活用すれば、より万全なタイミング法になるはずです。
排卵検査薬の判定に迷う時・注意点
排卵検査薬は便利な反面、「うまく判定できない」「結果の解釈に困る」などの戸惑いにつながることもあります。ここでは、そんな判定に迷いやすいケースや、検査薬を使う上で知っておきたい注意点についてまとめます。正しく理解して、不必要な混乱やミスを減らしましょう。
注意点1:検査前に水分を摂りすぎない
前述したように、水分の過剰摂取は検査結果に影響を与える大きな要因です。尿が薄まることでLH濃度も薄まり、本当は陽性レベルのLHサージが起きていても検査薬が反応しない可能性があります(いわゆる偽陰性)。特に夏場など喉が渇きやすい時期は注意が必要です。検査の少なくとも2時間前からは水やお茶、コーヒーなど利尿作用のある飲み物を控えるようにしましょう。どうしても軽い脱水が心配なときは、一口程度の水分を含んで潤す程度にとどめます。
また、「朝一以外の尿で」とされている理由も思い出してください。朝一番の尿は夜間に水分を取らず濃縮されているため、LH以外の不要な物質も濃く出てしまったり、あるいはLH濃度が高く出過ぎて検査薬が誤反応(偽陽性)することがあります。適度に水分を摂り日中動いている状態の尿の方が、体内の状況を反映したバランスの良い検体と言えるのです。「濃い尿=必ずしも良い結果」ではない点に注意し、適度に濃い尿で検査するのがコツになります。
注意点2:検査薬の感度や種類(デジタル式、スティック式)
市販されている排卵検査薬には様々な種類や感度の違いがあります。日本製・海外製を含め多くの製品がありますが、大きく分けるとスティック(または試験紙)タイプとデジタル表示タイプがあります。スティックタイプは判定窓にラインが出るオーソドックスな形式で、価格が比較的安価です。海外製の安価なものは試験紙だけのシンプルな製品もあり、たくさん本数を使う場合にコスト面で助かります。ただしラインの濃淡を自分で判定する必要があるため、慣れないうちは戸惑うかもしれません。一方、デジタルタイプは判定結果を笑顔マークや〇×などではっきり表示してくれるため判定ミスが起こりにくいのが利点です。こちらは1回あたりの単価が高めですが、初めて使う際に安心感があります。最初は日本製のデジタルや判定しやすい製品でコツを掴み、慣れてきたらコスト重視で海外製に切り替える…という使い分けをしている方もいるようです。
感度(LHに対する感受性)の違いも製品によりあります。例えば尿中LH20mIU/mL程度で陽性になる高感度なものから、40mIU/mL以上になって初めて陽性にするものまで様々です。高感度の方がLHサージを見逃しにくいメリットがありますが、その反面LHの基礎値が高めの人では常に薄く反応してしまい判定に悩むケースもあります(先述の「ずっと薄い線」の状態になりやすい)。自分に合った感度は使ってみないとわからない部分もありますが、「いつも薄い陽性止まりで困る」「逆に急に陽性が出て戸惑う」という場合、別のメーカーの検査薬を試してみるのも一つの方法です。最近では利用者の口コミ情報もネット上で見られるので、評判なども参考にしながらご自身に合いそうなものを選んでみてください。いずれにせよ、使用前には説明書をよく読み、各製品の判定基準に従うことが大切です。
ずっと陰性・陽性にならない場合
予定日から検査を始めてみたものの、いつまで経っても陽性反応が出ないという場合、いくつか考えられることがあります。まず一つは検査開始日が遅かった可能性です。実はすでにLHサージが終わった後に検査を始めてしまったため、残りの期間ずっと陰性のままだった…というケースですね。この場合、その周期はタイミングを逃してしまったことになりますが、次周期からはより早めに検査開始するよう調整しましょう。
次に考えられるのは、無排卵の周期である可能性です。女性の体はストレスや環境の変化などで一時的に排卵が起こらないことがあります。無排卵だと当然LHサージも起こらないため、検査薬は陰性のままとなります。基礎体温をつけていれば低温期が続くため無排卵だと気付きやすいですが、検査薬だけだと「ずっと陰性だな…おかしいな?」と不安になりますよね。心当たりがある場合(明らかに基礎体温が二相性になっていない、など)は、一度婦人科で相談してみましょう。生活習慣の改善アドバイスや必要に応じた薬物療法で排卵を促すことができます。
その他、検査のタイミングが合っていなかっただけの場合もあります。例えば本当は夜中にLHサージが起きたのに夕方の検査では陰性で見逃してしまった、などです。LHサージ自体は約1~2日間続くと言われますが、人によっては上昇から下降までが非常に短いこともあるようです。そのためどうしても1日1回の検査では捕捉しきれないケースがゼロではありません。心配な方は1日2回(朝と夕方など)に増やしてみるのも手です。ただし前述のとおり、同じ人で何度もLHサージを見逃す(偽陰性が繰り返される)ことは稀とも言われます。毎周期まったく陽性が出ない状況が続くなら、自己判断せず専門医に相談することをおすすめします。
ずっと陽性(またはうっすら陽性)が続く場合
逆に、検査薬が連日陽性のままだったり、明確な陽性ではないにせよ常に薄い線が出続けている場合も考えられます。通常、LHサージは長くても2日程度で収束するため、陽性反応が3日以上連続するのはあまり一般的ではありません。このような場合に疑われる要因として、次のようなものがあります。
多嚢胞性卵巣症候群(PCOS)の可能性
多嚢胞性卵巣症候群(PCOS)とは、卵巣内に多数の小さな卵胞が存在することでホルモンバランスに乱れが生じ、排卵がうまく起こりにくくなる疾患です。PCOSの女性はLH値が慢性的に高めであることが多く、排卵検査薬が常に反応してしまう場合があります。結果として「ずっと陽性みたいな反応が出る」「いつが本当のピークか分からない」といった状況になりがちです。さらにPCOSでは排卵自体が起こらないか非常に遅れることも多いため、検査薬だけで妊娠のタイミングを図るのは困難です。もし月経不順や毛深さ・ニキビ等PCOSに心当たりがある症状がある場合、早めに婦人科で診察を受けてみましょう。適切な治療により排卵を誘発し、タイミング指導を受けることができます。
LHの基礎値が高いケース
PCOSでなくとも、もともと体質的にLH値がやや高めの方もいます。この場合も、排卵期でなくても常に検査薬が薄反応してしまうことがあります。例えば検査薬の感度が高すぎて通常時のLH分泌でも基準ライン近くに達してしまう…というケースです。そのため「ずっと薄く陽性っぽい線」が出続け、どこが本当のサージなのか判定しにくくなります。対策としては、少し感度の低い検査薬に変えてみることが挙げられます。感度が低ければ普段のLHには反応せず、本当のサージ時だけ陽性になる期待が持てます。薬局で購入する際に感度まではわからないかもしれませんが、製品によって反応しやすさが異なるので、いくつか試して相性の良いものを見つけると良いでしょう。
排卵検査薬は妊娠検査薬ではありません
最後に、排卵検査薬と妊娠検査薬の混同について注意喚起しておきます。稀に「排卵検査薬で陽性が出たけど生理が遅れている。もしかして妊娠?」「排卵検査薬で妊娠が分かるって本当?」といった声を聞きます。しかし、排卵検査薬はあくまでLHホルモンを検出するものです。一方、妊娠検査薬が検出するのはhCG(ヒト絨毛性ゴナドトロピン)というホルモンで、これはLHとは別物です。構造が似ているため「排卵検査薬で妊娠反応が出ることもある」と言われることがありますが、極めて不確実です。仮に妊娠していたとしても排卵検査薬では正確な判定はできませんし、逆にLHサージが強かっただけなのに「妊娠かも?」と勘違いしてしまうリスクもあります。妊娠の有無を調べたい時は、必ず妊娠検査薬を使用しましょう。 排卵検査薬は妊娠検査薬の代わりにはなりません。それぞれ目的が異なる道具ですので、使い分けをしてくださいね。
排卵検査薬を使っても妊娠しない…クリニックに相談するタイミング
「排卵検査薬を使ってタイミングも合っているはずなのに、なかなか妊娠しない…」という場合、そろそろ専門家に相談すべきか悩むことでしょう。ここでは、排卵検査薬では解決できない要因や、受診の目安について説明します。妊活の方が適切なタイミングで次のステップに進めるよう、お役立てください。
排卵検査薬で陽性が出ても排卵していない可能性
前述のとおり、排卵検査薬の陽性は「排卵直前のサイン」ではありますが、実際に確実な排卵が起こったかどうかまでは保証していません。中には「LHサージはあったが卵胞が破裂しなかった」というケースも存在します。黄体化未破裂卵胞(LUF)と呼ばれる現象で、卵胞が成熟してLHサージも起きたのに排卵だけ起こらず、卵胞がそのまま黄体化してしまう状態です。このような場合、検査薬では陽性反応が出ますが卵子は放出されていないため受精は起こりません。LUFは頻度の高いものではありませんが、もし排卵検査薬の結果通りにタイミングをとって半年以上妊娠しない場合、念のため医療機関で排卵の有無をチェックしてもらう価値があります。超音波検査やホルモン血液検査で排卵がきちんと起きているかを確認できるので、自己判断で悩み続けるより安心につながります。
どのくらいの期間、自己流で試していい?
排卵検査薬を駆使してタイミング法を続けていても妊娠に至らないとき、「一体いつまでこのまま頑張ればいいの?」と不安になりますよね。受診の目安については、年齢によって異なることが一般的に提案されています。
35歳未満の方は1年が目安
医学的には、避妊せず性交渉を続けて1年経っても妊娠しない状態を「不妊症」と定義します(35歳以上では6か月、次項参照)。そのため、まだお若く時間的余裕のある方(目安として女性側が35歳未満)は、1年程度は自己流のタイミング法で妊娠を目指してみてもよいでしょう。1年間で大体90%のカップルが自然妊娠すると言われていますから、逆に言えば1年経っても妊娠しない約10%の場合には何かしら原因が潜んでいる可能性があります。もし1年を迎えても授かっていなければ、不妊の原因検査のために一度クリニックを受診することを検討しましょう。
35歳以上の方は半年の使用を目安に
女性の妊娠率は35歳頃から徐々に低下し始め、40歳以降で大きく低下するとされています。そのため35歳以上で妊活中の方は、約6か月(半年)試してみても妊娠しない場合には早めに専門医に相談するのが望ましいとされています。これは海外の生殖医学会などでも推奨されている目安です。年齢が上がるほど時間の経過が妊娠の確率に影響しますから、「もう少し頑張れば…」と自己流を続けすぎるのは得策ではありません。不妊治療=すぐ高度な治療をするという意味では決してなく、まずは原因がないか検査し、タイミング法の見直しや必要なサポートを受けることが大切です。思い切って一歩踏み出してみましょう。
判定に自信が持てない、月経不順がある場合
排卵検査薬を使ってはいるものの、自分ではどうも判定に自信がない、あるいは月経不順でタイミングの自己判断が難しいという場合も、早めにクリニックで相談してみましょう。専門家のサポートを受ければ、無駄な遠回りを減らすことができます。判定に迷う場合は、実際に使用した検査薬(判定窓の部分)や記録したメモを持参すると医師も状況を把握しやすくなります。「このくらいの濃さでタイミングを取ったけど合っていたか?」など遠慮なく質問してみてください。月経不順の場合も、排卵誘発剤で周期を整えながら検査薬を使う方法など、一人で悩むより適切なアドバイスが得られるでしょう。
パートナー(男性)の検査も大切です
忘れがちですが、妊活では男性側の検査・対策も重要です。排卵検査薬は女性の排卵タイミングを把握するためのものですが、いくらタイミングが合っても精子の状態に問題があれば妊娠には至りません。不妊の原因は男女半々と言われますので、一定期間妊娠しなければ男性も精液検査を受けることが推奨されます。これは泌尿器科や不妊外来で受けられる検査で、精子の数や運動率などを調べるものです。女性が一生懸命検査薬で頑張っているのですから、ぜひパートナーにも協力してもらいましょう。男性側に問題が見つかれば、タイミング法以外のアプローチ(人工授精や体外受精など)を検討する必要が出てきます。早めに状況を把握しておくことが大切です。
レディースクリニックなみなみでできる正確な排卵予測
排卵検査薬は便利ですが、もっと確実かつ詳細な排卵の予測や、妊娠しやすい環境作りのサポートを受けたい場合、医療機関での検査・指導が有効です。ここでは当院(レディースクリニックなみなみ)で提供している排卵予測の方法をご紹介します。自己流のタイミング法に限界を感じたら、ぜひ専門家の力も活用してみてください。
超音波(エコー)検査による卵胞チェック
産婦人科では経腟超音波(エコー)検査を用いて卵巣内の卵胞発育をモニタリングすることができます。卵胞は排卵に向けて徐々に大きくなり、通常18~20mm程度に成熟すると排卵が近いサインとなります。超音波検査なら卵胞の大きさをミリ単位で正確に測定できるため、「卵胞が充分育っているか」「あと何日くらいで排卵しそうか」を高い精度で予測できます。例えば通院して数日おきに卵胞チェックを行い、「卵胞が20mmになったので明日か明後日排卵でしょう」など具体的なタイミングを医師がお伝えします。これは排卵検査薬よりも確実性が高く、特に生理不順の方や検査薬でうまく陽性が出ない方に有効です。
ホルモン検査(血液検査)による排卵予測
血中のホルモン値を測定することでも、より正確な排卵のタイミング予測が可能です。排卵が近づくとLHだけでなくエストロゲン(卵胞ホルモン)も上昇しますし、排卵後にはプロゲステロン(黄体ホルモン)が増えます。クリニックでは採血によりこれらホルモン濃度をチェックし、総合的に判断することができます。例えば「LHが急上昇してきたからもうすぐ排卵しそうだ」「排卵後の黄体ホルモン値もしっかり上がっているからちゃんと排卵している」といった具合です。尿で測る簡易検査薬と異なり数値として客観的に出るので、より信頼度の高い情報が得られます。必要に応じて何日か連続で採血し、ホルモンの変化を追うことで排卵日を高い精度で割り出すことも可能です。
医師による正確なタイミング指導
超音波検査やホルモン検査の結果を踏まえて、医師がタイミング指導(性交渉のタイミングの具体的な指示)を行います。「◯月◯日の夜と翌朝にタイミングを取ってみましょう」「次の来院日は◯日後にしてください」など、個別の状況に合わせたアドバイスを受けられるのはクリニックならではです。また、排卵に合わせて排卵誘発の注射を使用することもあります。これはHCG製剤などを用いて排卵を促すもので、「明日排卵させたい」という時に行い、計画的にタイミングを合わせることができます。こうした医療的サポートにより、自己流では難しかった細かな調整や不安の軽減が期待できます。「毎周期うまくいっているか自信がない…」と感じているなら、一度専門的なタイミング指導を受けてみてはいかがでしょうか。妊活のプロである医師・スタッフが、しっかりあなたをサポートいたします。
まとめ:排卵検査薬を正しく理解し、ご自身の体を知ることから始めましょう
排卵検査薬は、妊活において心強い味方となるツールです。正しく使えば排卵のタイミングをしっかり捉えられますし、自分の体のリズムを知る助けにもなります。今回解説したように、使い始める時期や検査のコツ、陽性・陰性の判断基準、タイミングの取り方、そして起こり得るトラブルや注意点をあらかじめ知っておくことで、不安や迷いはかなり軽減できるはずです。
一方で、排卵検査薬はあくまで補助的なツールであり、妊娠の保証をするものではないことも事実です。うまく活用しても妊娠に至らないときは、決して自分を責めたり落ち込んだりしないでくださいね。妊娠にはタイミング以外にも様々な要因が関与します。大切なのは必要に応じて専門家の力を借りることです。「もしかして不妊かも」と一人で抱え込まず、早めに婦人科を受診してみましょう。私たちレディースクリニックなみなみでは、タイミング法で頑張るあなたを全力でサポートいたします。排卵検査薬の結果の見方に不安がある方、思うように妊娠できず悩んでいる方は、どうぞお気軽にご相談ください。あなたの妊活を専門医療の面から支え、安心して前に進めるようお手伝いいたします。妊娠への第一歩は、自分の体を知ることから始まります。排卵検査薬を上手に取り入れて、ぜひあなたのペースで妊活に取り組んでいきましょう。安心して一緒に頑張っていけるよう、私たちも応援しています。
レディースクリニックなみなみを予約する排卵検査薬に関するよくあるご質問(FAQ)
排卵検査薬はどこで購入できますか?費用はどのくらいですか?
排卵検査薬はドラッグストアの薬剤師カウンターや、インターネットの医薬品販売サイトで購入できます。2016年から一般用医薬品(第1類)として薬局で取り扱われるようになりました。ただし第1類医薬品のため、店舗では薬剤師がいる時間帯でないと販売してもらえません。また通販でも購入前にメールや電話で薬剤師の説明を受ける手続きが必要です。費用は製品や本数によりますが、5回分で2,000~3,000円前後、10回分で3,000~4,000円前後が一つの目安です。デジタルタイプはやや高価ですが判定が分かりやすく、ライン判定タイプは比較的安価です。海外製の簡易タイプはさらに安いものもあります。ご自身の使いやすさと予算に合わせて選ぶと良いでしょう。なお、当院でも院内処方で排卵日検査薬をお出しすることがありますが、基本的には市販品で十分対応できます。
基礎体温のグラフと排卵検査薬の結果が食い違うように思います…。どちらを信じればいいですか?
基礎体温と排卵検査薬は、それぞれ見るポイント(タイミング)が異なるため、多少結果がずれることがあります。排卵検査薬は「これから排卵しそう」を示し、基礎体温は「排卵が終わった後(高温期になった)」を示します。一般的には、排卵検査薬の陽性が出た日~翌日に排卵し、その翌日から体温が上がり始める流れです。しかし体温はストレスや睡眠不足でも変動し、必ずしもきれいに二相に分かれない場合もあります。「排卵検査薬では陽性が出たのに、体温が上がるのが2日後だった」「体温は上がったのに検査薬が陽性にならなかった」などのケースも珍しくありません。基本的には排卵検査薬のタイミングを優先して構いませんが、基礎体温で高温期に入ったことを確認できればより安心です。何周期か試してみて、あまりにも食い違うようなら一度医師にご相談ください。基礎体温から黄体機能の状態が分かることもありますので、両方の情報を合わせて判断してもらうと良いでしょう。
排卵痛があるのですが、排卵検査薬の結果とどちらを信じればいいですか?
排卵痛(排卵時に感じる下腹部のチクッとした痛み)は、人によって有無や感じ方が異なります。もしご自身が毎周期排卵痛を感じるタイプで、かつそれが明確に分かるのであれば、一つの目安にはなります。ただし排卵痛のタイミングは必ずしも実際の排卵とピタリ一致するとは限りません。痛みを感じるのは排卵前後どちらの人もいますし、中には排卵と関係のない卵巣周囲の違和感を排卵痛と認識している場合もあります。客観性という点では、排卵検査薬の結果の方が信頼できる指標です。ですから基本的には検査薬の陽性反応に従ってタイミングを取り、排卵痛は「あ、何か痛いな。もう排卵したかな?」くらいの参考情報に留めると良いでしょう。もちろん強い痛みが続く場合は別のトラブルの可能性もありますから、その際は医師に相談してください。
排卵検査薬は保険適用になりますか?
現在、排卵日予測検査薬そのものは保険適用の対象外となっています。以前は医師の処方せんがあれば保険で入手できることもありましたが、一般用医薬品に移行した現在は自費で購入する形が基本です。ただし、不妊症の治療過程で医師が必要と認めた場合に限り、医療保険の不妊治療の範囲で排卵日の予測に関する指導が受けられることはあります。例えばタイミング法の指導料や、排卵日特定のための超音波検査・ホルモン検査等は保険適用になるケースがあります。しかし市販の検査薬を買う費用そのものは自己負担となります。経済的負担が大きい場合は、一度自治体の不妊治療助成制度なども調べてみると良いでしょう。市販薬代は対象外かもしれませんが、今後ステップアップ治療を検討する際の参考になるかもしれません。
排卵検査薬で陽性になったら、何日間タイミングを取ればいいですか?
排卵検査薬が陽性になったら、少なくともその日と翌日の2日間は連続してタイミングを取ることをおすすめします。人によっては翌々日までタイミングを持つと安心かもしれません。前述のとおり、陽性当日~翌日が妊娠確率の高いタイミングだからです。例えば夜に陽性を確認した場合、当日夜と翌日夜の2回を目標にすると良いでしょう。もし体力的につらい場合はどちらか1回でも構いません。逆に余裕があれば翌々日もチャレンジしてください。注意点として、事前に何日も禁欲した精子よりも、2~3日以内に放出された精子の方が受精能力が高いと言われます。そのため陽性が出たからといって慌てて長期間溜める必要はなく、タイミングは毎日でも大丈夫です。パートナーと相談し、無理のない範囲で取り組んでみてください。
参考文献
日本産科婦人科学会/日本産婦人科医会『産婦人科診療ガイドライン 婦人科外来編2023』(2023年)
厚生労働省『黄体形成ホルモンキットに係る一般用検査薬ガイドライン』(2016年)
公益社団法人日本産科婦人科学会『不妊症(定義に関する見解)』(2025年)
一般社団法人日本生殖医学会『生殖医療Q&A』(2025年)
政府広報オンライン『不妊治療、社会全体で理解を深めましょう』(2023年)
Li Sほか『黄体化未破裂卵胞(LUF)が胚移植転帰に与える影響』(2021年)

執筆者兼監修者プロフィール
東大産婦人科に入局後、長野県立こども病院、虎の門病院、関東労災病院、東京警察病院、東京都立豊島病院、東大病院など複数の病院勤務を経てレディースクリニックなみなみ院長に就任。
資格
- 医学博士
- 日本産科婦人科学会 産婦人科専門医
- FMF認定超音波医
…続きを見る