
執筆者兼監修者プロフィール
東大産婦人科に入局後、長野県立こども病院、虎の門病院、関東労災病院、東京警察病院、東京都立豊島病院、東大病院など複数の病院勤務を経てレディースクリニックなみなみ院長に就任。
資格
- 医学博士
- 日本産科婦人科学会 産婦人科専門医
- FMF認定超音波医
…続きを見る
妊娠初期に「出生前診断を受けるべきか」と迷う方は少なくありません。出生前診断とは、お腹の赤ちゃんに異常がないか妊娠中に調べる検査のことで、超音波検査や母体血液検査、羊水検査などいくつかの方法があります。近年は新型出生前診断(NIPT)と呼ばれる母体血を使った検査が普及しつつありますが、日本ではすべての妊婦さんに義務づけられているわけではなく、自分で希望して受ける任意の検査です。
どのくらいの妊婦さんが出生前診断を受けているのか、出生前診断にはどんなメリット・デメリットがあるのか、受けるべきなのか悩む方に向けて解説します。
出生前診断は受けるべきか?
結論から言えば、出生前診断を受けるかどうかは妊婦さん本人とパートナーの意思で決めるものです。出生前診断は希望者が任意で受ける検査であり、受けるかどうか「べき」と一概には言えません。妊娠中の赤ちゃんの状態を知ることで安心できる人もいれば、知らずに出産を迎えたいと考える人もいます。
出生前診断の結果はご家族にとって重要な情報をもたらしますが、ときに難しい決断を迫られる可能性もあります。検査で異常の可能性を指摘されると不安や迷いが生じ、「検査を受けなければよかった」と感じる人がいる一方で、検査を受けずに出産し後から赤ちゃんの病気が判明して「やはり検査をしておけばよかった」と感じる人もいます。そのため、出生前診断を受けるか否かはメリットとデメリットを理解した上で、後悔の少ない選択をすることが大切です。分からないことがあれば遠慮せず産婦人科医や遺伝カウンセラーに相談し、自分たちにとって納得のいく決断をしましょう。
出生前診断を受ける人の割合
厚生労働省の専門委員会が2020年に行ったアンケート結果では、35歳未満の妊婦さんではNIPT受検率はわずか2.4%、35歳以上の妊婦の約10.2%、40歳以上では22.7%がNIPTを受けたと回答しており、高齢妊娠になるほど受検率が高くなる傾向が示されています。日本における出生前診断(染色体異常を調べる検査)実施率は、欧米と比べると低いものの年々増加しています。
さらに「将来妊娠するなら出生前検査を受けたい」と考える人は男女とも半数以上いたとの報告もあり、今後は情報提供の充実や高齢出産の増加に伴い検査を受ける人の割合はさらに増えていくと予想されています。
出生前診断とは?
出生前診断とは、妊娠中に赤ちゃんの先天的な異常の有無を調べる検査の総称です。代表的なものには、超音波検査(エコー)や母体血清マーカー検査、新型出生前診断(NIPT)、絨毛検査、羊水検査があります。内容的にはスクリーニング検査(非確定的検査)と確定診断検査に大別されます。
スクリーニング検査
赤ちゃんの異常の「可能性」を調べる検査です。妊婦健診で行われる超音波検査も広い意味では出生前診断の一種で、赤ちゃんの形態的な奇形や発育状況を観察します。また母体血清マーカー検査(いわゆるクアトロテストなど)は母体の血液成分を分析し、21トリソミー(ダウン症候群)や18トリソミー(エドワーズ症候群)などの確率を推定します。NIPT(非侵襲的出生前遺伝学的検査)もスクリーニング検査の一種で、妊婦さんの血液中にわずかに含まれる胎児由来DNAを解析し、ダウン症候群(21トリソミー)、エドワーズ症候群(18トリソミー)、パトウ症候群(13トリソミー)などの染色体数の異常を高精度に判定します。NIPTは妊娠10週以降という早い時期から受けられること、そして母体の血液を採取するだけで済む安全性の高さが大きな特徴です。
確定診断検査
胎児の細胞そのものを調べて異常の有無を確定的に診断する検査です。代表は絨毛検査と羊水検査で、いずれもお腹に細い針を刺して試料を採取するため侵襲的検査となります。絨毛検査は胎盤の一部である絨毛細胞を採取して行う検査で、妊娠11~14週頃に実施可能です。羊水検査は羊水中の胎児細胞を採取する検査で、妊娠16~18週頃に行われます。いずれも胎児の全染色体を調べることができ、染色体の数や構造の異常をほぼ100%の精度で診断できます。確定診断は精度が高い反面、絨毛検査では約1%、羊水検査では0.2~0.3%程度の流産リスクが報告されています。
出生前診断のメリット
出生前診断にはどのようなメリットがあるのでしょうか。主なポイントは次の2つです。
① 赤ちゃんの状態を確認できる
出生前診断を受ける最大のメリットは、お腹の赤ちゃんの健康状態について妊娠中に情報を得られることです。検査によって赤ちゃんに特定の異常が「あるかもしれない」または「ないらしい」と分かれば、漠然とした不安を減らし心構えができるでしょう。実際に2020年の厚生労働省の調査では、「胎児について多くのことを知るのは良いこと」「検査で異常が見つからなければ安心できる」と考える女性が多数派でした。特にNIPTのような検査精度の高い方法で「異常の可能性が低い(陰性)」という結果が得られれば、多くの妊婦さんは安心して妊娠生活を送ることができます。
一方、仮に出生前診断で赤ちゃんの異常の可能性が示唆された場合でも、事前に知っておくことで心の準備を早めに始められるというメリットがあります。何も知らずに出産当日を迎えて急に知らされるより、妊娠中に分かっていれば徐々に受け入れる時間を持てるでしょう。また、結果を受けてさらに調べたい場合には羊水検査など追加の検査を行う選択肢もとれます。このように、出生前診断を通じて赤ちゃんの状態をあらかじめ把握できること自体が大きな意義と言えます。
② 赤ちゃんの状態に合わせた準備ができる
出生前診断でもし赤ちゃんの病気や障害が判明した場合、出産前から医学的に必要な準備を進められることも重要なメリットです。例えば、赤ちゃんに心疾患などの問題が見つかったときは、分娩方法を帝王切開に切り替えたり、生まれた直後に治療が受けられるようNICU(新生児集中治療室)のある高度医療機関で出産したりといった対応が可能です。実際に出生前に赤ちゃんの疾患が分かれば、産科から小児科・小児外科への引き継ぎを円滑に行い、赤ちゃんに必要な処置を速やかに開始できます。また、自宅で育てる環境を整えたり、公的支援制度について情報収集したりと、産む前からできる備えもたくさんあります。
このように赤ちゃんの異常を事前に知ることで、その後の対策を早期から検討し十分に備えられる点は、家族にとって大きな安心材料です。高リスク妊娠の場合には分娩先を変更する判断もしやすくなりますし、周囲の家族にも心づもりをしてもらうことができます。「もし赤ちゃんに何かあっても受け入れる準備をしておきたい」という思いから出生前診断を受ける人は多く、実際厚労省の調査でも「胎児が病気だったら早く準備ができるから」という理由で検査を望む人が65%にのぼったと報告されています。
出生前診断のデメリット
一方で、出生前診断には注意すべきデメリットやリスクもあります。主なポイントを2つ解説します。
① 結果で混乱したり不安になったりする場合がある
出生前診断の結果は精神的な負担を伴う場合があります。とくにスクリーニング検査で「陽性(高リスク)」と判定された場合、確定診断のために羊水検査を受けて結果を待つ間は強い不安を感じるでしょう。また陽性の場合、赤ちゃんを迎えるか中絶するかといった非常に困難な決断を迫られることがあります。そのプレッシャーから「検査を受けなければよかった」と後悔する妊婦さんも実際にいらっしゃいます。出生前診断のデメリットとしてまず挙げられるのは、こうした心理的ストレスの大きさです。
さらに、出生前診断の結果にはグレーゾーンや誤判定の可能性もある点に留意が必要です。スクリーニング検査の結果「陽性」と言われても、実際には赤ちゃんが正常で、検査が間違っていた(偽陽性)ケースや、その逆に「陰性」と言われても見落としがあった(偽陰性)ケースもゼロではありません。疑いが残る場合には最終的に侵襲的な検査で確認するしかなく、確定診断の羊水検査等にはわずかながら流産のリスク(約0.3%)も伴います。このように、出生前診断を受けることは妊婦さんの心身に多少なりとも負担をかけるものであり、その点はデメリットと言えるでしょう。
② 検査ですべての病気は分からない
出生前診断で分かることには限界がある点もデメリットとして認識しておきましょう。前述の通り、出生前診断の主な対象は染色体数の異常など一部の先天疾患です。超音波検査やNIPTで異常の指摘がなくても、出生前診断では調べられない種類の病気(例えば自閉症や発達障害、極めてまれな遺伝子疾患など)が将来見つかる可能性は残ります。また超音波検査で確認できる胎児の形態も、妊娠週数や胎位によっては全てを把握できるわけではありません。出生前診断の結果が「異常なし」でも、赤ちゃんの健康が完全に保証されたわけではないことを理解しておく必要があります。
反対に、検査で分かった異常に対しても限界があります。例えばNIPTで判明するのは主に特定の染色体異常ですが、診断が確定するわけではないため陽性の場合は追加の検査が必要です。確定診断の羊水検査や絨毛検査まで行えば多くの染色体疾患は判明しますが、それでも検査できる範囲外の異常(超微細な遺伝子変異など)は発見できないことがあります。つまり出生前診断ですべてが分かるわけではなく、100%の安心は得られないのです。この点を誤解していると、「検査で大丈夫と言われたのに赤ちゃんに病気が見つかってショック」という事態にもなりかねません。検査の限界を踏まえた上で活用することが大切です。
出生前診断の費用
出生前診断の費用は検査の種類によって大きく異なります。日本では基本的に出生前診断は公的医療保険が適用されず自費診療となるため、全額自己負担で数万円から数十万円の費用がかかります。
施設によって差がありますが、しっかりした遺伝カウンセリング体制を整えた認可施設では20万円前後、検査項目を絞ったプランを提供するクリニックでは10万円前後など、内容によって幅があります。
母体血清マーカー検査(クアトロテストなど)の費用は約2~3万円程度と比較的安価です。こちらも自費診療ですが、一部自治体では高齢妊婦に対して助成制度がある場合もあります。検査可能な時期は妊娠15~18週頃とやや後期になります。
胎児ドック(出生前超音波スクリーニング検査)は施設によりますが、基本料金が約3~5万円ほどで、追加の精密検査料が数千円~数万円かかるケースがあります。高精細エコーや母体血マーカーとの組み合わせで行う総合的なスクリーニングで、こちらも保険適用外です。
羊水検査・絨毛検査(確定診断)は約10~20万円程度の費用がかかります。検査自体の費用に加え、施行施設によっては数日間の入院費が別途発生することがあります。なお、出生前診断で陽性(要精密検査)となり確定診断を行う場合、その結果次第では母体保護法にもとづく処置(人工妊娠中絶)となる可能性がありますが、中絶手術費用も健康保険がきかず自己負担となります。
出生前診断はメリットとデメリットを理解して受けるか検討しましょう
出生前診断を受けるべきか迷うのは当然のことです。検査には赤ちゃんやご家族にとって良い面(メリット)と注意すべき面(デメリット)の両方があります。本記事で解説した通り、出生前診断を受けることで得られる安心感や準備期間は大きなメリットですが、一方で結果に向き合う覚悟や検査の限界も踏まえておかなければなりません。大切なのはメリットとデメリットを十分に理解し、自分たちにとって最善と思える選択をすることです。
レディースクリニックなみなみでは、妊婦さん一人ひとりの気持ちに寄り添いながら、安全で適切な周産期医療を提供しています。出生前診断について不安や疑問があれば、どうぞお気軽にご相談ください。検査を受ける・受けないのどちらの選択であっても、納得してマタニティライフを送れるようスタッフ一同サポートいたします。赤ちゃんとお母さんが健やかに出産の日を迎えられるよう、お手伝いさせていただきますね。
レディースクリニックなみなみを予約する出生前診断に関するよくある質問
出生前診断を受けなかったことで後悔した人はいる?
個人差はありますが、出生前診断を受けなかったことで後悔する人はいます。
出生前診断を受けずに出産し、生まれた赤ちゃんに予期せぬ疾患が見つかった場合、「事前に分かっていれば心の準備や対応ができたのに…」と感じる方もいるでしょう。特に高齢出産でリスクが高い場合や、家族に遺伝性疾患がある場合などは、検査を受けなかったことを後悔するケースが考えられます。
出生前診断について病院から言われないと受けられない?
いいえ、病院から勧められなくても自分の意思で受けることが可能です。日本では現在、妊婦健診の中で必ず出生前診断の案内があるわけではなく、病院によって対応は様々です。NIPTは開始当初、35歳以上など一定の条件を満たす妊婦に対して認可施設で提供されていた経緯があり、担当医から話がなければ受けられないものと誤解されがちです。しかし実際には希望者であれば年齢にかかわらず検査を受けることはできます。
注意点として、出生前診断を扱っていない産院もあるため、自分の通院先で検査が可能かどうか確認が必要です。最近では認可外のクリニックも含めNIPT検査施設が増えていますが、NIPTのみのクリニックは基本的にフォロー体制や説明が不十分なところが多いので注意が必要です。
出生前診断はいつまでに受ける必要がある?
スクリーニング検査のNIPTは妊娠10週以降から受けられます(多くの施設では15~16週くらいまでに実施)。絨毛検査は妊娠11~14週頃まで、羊水検査は16~18週頃までが適した時期です。母体血清マーカー検査(クアトロテスト)は妊娠15~20週に行われます。
日本では母体保護法にもとづく人工中絶は妊娠21週6日まで(概ね妊娠22週未満)と定められており、胎児の重篤な異常で妊娠継続が困難と判断される場合も、この時期までに決断する必要があります。したがって、できるだけ妊娠初期から中期前半までに出生前診断を受け、必要なら追加の検査を経て20~21週頃までに結果を得ることが望ましいでしょう。もちろん検査を受ける目的は中絶だけではなく出産準備のためという方も多いですが、いずれにせよ妊娠後期に入るとできる検査が限られてしまいます。

執筆者兼監修者プロフィール
東大産婦人科に入局後、長野県立こども病院、虎の門病院、関東労災病院、東京警察病院、東京都立豊島病院、東大病院など複数の病院勤務を経てレディースクリニックなみなみ院長に就任。
資格
- 医学博士
- 日本産科婦人科学会 産婦人科専門医
- FMF認定超音波医
…続きを見る
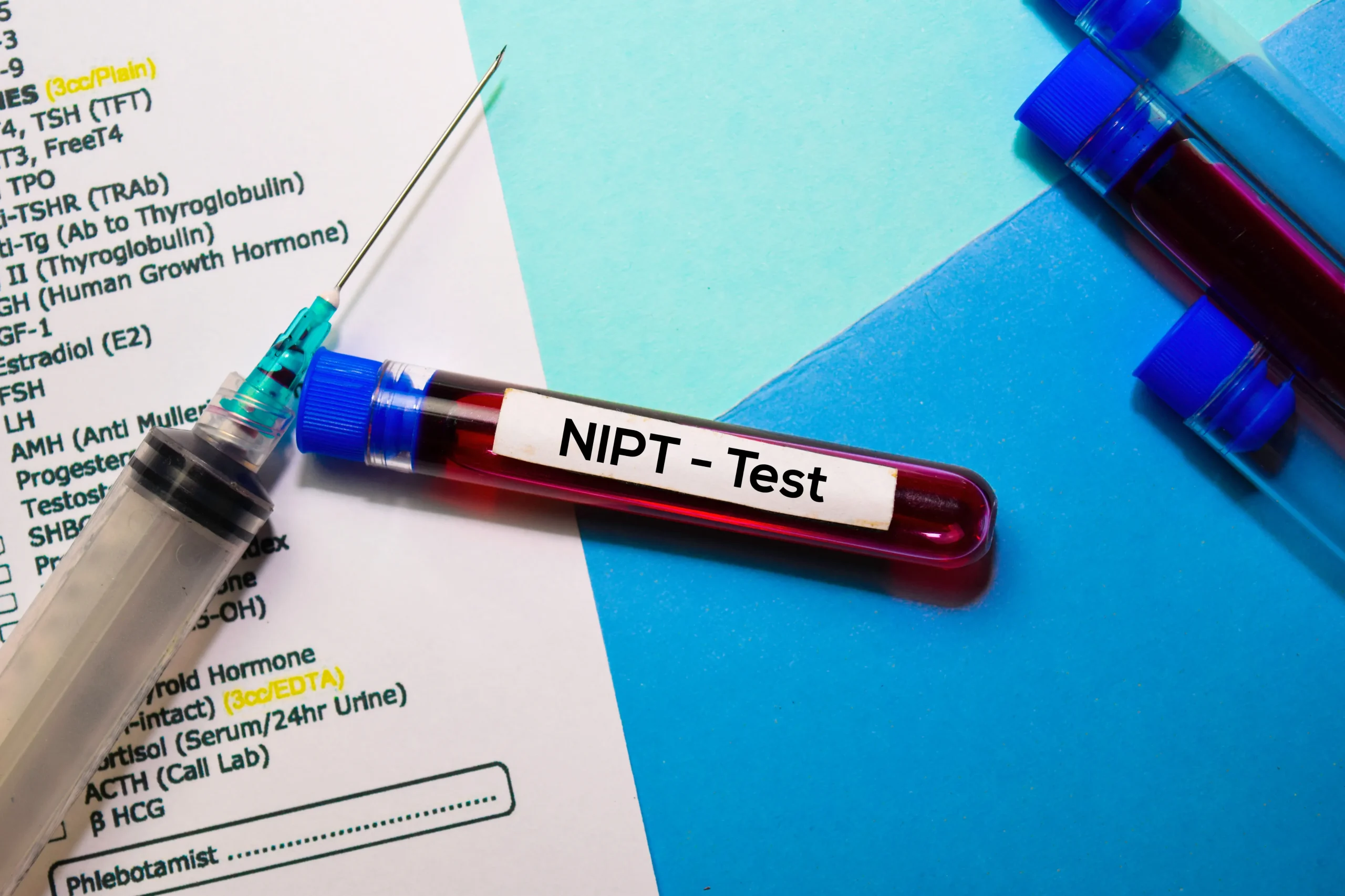












出生前診断で主に調べられるのは赤ちゃんの染色体異常です。具体的には先述のダウン症候群、エドワーズ症候群、パトウ症候群などのほか、性染色体の異常(例:ターナー症候群、クラインフェルター症候群)や、一部の検査では染色体の微小な欠失・重複といった異常まで対象になります。超音波検査では染色体異常が疑われる所見(胎児の首のむくみ〈NT肥厚〉や心奇形など)や、無脳症・二分脊椎といった形態的異常の有無もチェックできます。ただしいずれも出生前診断で分かる疾患には限りがある点には注意が必要です。検査結果が正常でも、出生前診断で調べられない病気や障害については赤ちゃんが生まれるまで分からないこともあります。