
執筆者兼監修者プロフィール
東大産婦人科に入局後、長野県立こども病院、虎の門病院、関東労災病院、東京警察病院、東京都立豊島病院、東大病院など複数の病院勤務を経てレディースクリニックなみなみ院長に就任。
資格
- 医学博士
- 日本産科婦人科学会 産婦人科専門医
- FMF認定超音波医
…続きを見る
着床前検査(PGT)は有用な技術ですが、高額な費用負担や検査精度の限界、倫理的な問題などいくつかのデメリットも存在します。さらにPGTは妊娠後の出生前診断(NIPTなど)を完全に不要にするものではなく、PGT後も追加の検査が推奨されるケースがあります。費用や保険適用の状況、他の検査との違いを正しく理解し、メリット・デメリットを踏まえて活用することが大切です。
PGTに興味はあるものの、「本当にやるべきか」「お金に見合う効果があるのか」「倫理的に問題はないのか」など迷いを感じている方も多いでしょう。また、PGTを受けた後もNIPT(新型出生前診断)や羊水検査が必要かどうか、不安に思うかもしれません。ここではそうした疑問や不安に答え、PGTのデメリットや他検査との比較、費用面の情報を詳しくお伝えします。
この記事でわかること:
- 着床前検査(PGT)のデメリット・限界(高額な費用、検査の精度やリスク、倫理的課題など)
- 着床前検査と出生前診断(NIPTや羊水検査など)の違い(タイミングや対象、目的の比較)【比較表あり】
- PGTにかかる費用の相場と保険適用の有無、自治体の助成金制度の情報
- PGT後にNIPT等の出生前診断は必要か?PGTを受けた後の注意点
PGTのデメリット・限界
着床前検査(PGT)には多くの利点がある一方で、いくつかのデメリットや技術的限界も存在します。ここではPGTを検討する上で知っておきたい主なデメリットを挙げます。
費用負担が非常に大きい
PGT最大のハードルは検査費用の高さです。1回のPGTに50〜100万円程度かかるのが相場であり、体外受精自体の費用(数十万円)に加えてさらに高額な費用負担となります。検査する胚の数が多いほど費用は増え、複数回の採卵や複数サイクルに及べばトータルの支出は数百万円に達することもあります。このようにPGTは経済的負担が非常に重い治療です。しかも現時点では公的医療保険が適用されず、全額自己負担となります。2022年4月から不妊治療の一部(体外受精の基本部分)は保険適用になりましたが、PGTは薬事未承認の検査機器を用いることや倫理面の問題から公的保険の対象外とされています。そのため費用面のデメリットは避けられません。ただし、後述するように一部自治体ではPGTに対する助成金制度が設けられている場合があります。経済的負担を理由にPGTを断念せざるを得ないケースもあるため、費用に見合う効果が得られるか慎重に検討する必要があります。
利用できる施設が限られる
PGTは実施できる医療機関が少なく、希望しても受けられるクリニックが限られているのが現状です。日本産科婦人科学会の管理下で行われている関係上、学会認定の限られた施設(vol1の記事を参考にしてください▶)でしか取り扱っていません。大都市圏の一部不妊治療専門クリニックに集中しており、地域によっては該当施設がゼロということもあります。そのため遠方への長期通院が必要になる場合や、施設の選択肢が乏しいというデメリットがあります。また、PGT-Mは症例ごとに準備が必要なため、申し込んでから実施までに時間がかかります。誰もがすぐ受けられる検査ではない点も押さえておく必要があります。
検査結果は確実ではない(偽陰性・偽陽性の可能性)
PGTの検査精度は年々向上していますが、100%正確な結果を保証するものではありません。例えばPGT-Aでは胚の一部の細胞を検査して正常と判断しても、胚の別の部分に異常細胞が残っている「モザイク胚」のケースがあります。この場合、PGTでは正常と判定され移植された胚でも、一部異常が胎児に影響を及ぼす可能性があります(結果的にNIPTで異常シグナルが出ることもあります)。逆に、本当は子宮に戻せば発育可能だった軽度のモザイク胚をPGTで「異常」と判定し捨ててしまうリスク(偽陽性)も指摘されています。PGT-Mでも、ごく稀に分析エラーや家系由来の遺伝子多型の影響で誤判定が起こる可能性があります。こうした偽陰性・偽陽性のリスクは低いもののゼロではなく、PGTの限界として認識しておくべきです。このためPGTで正常と判定された後も、妊娠中には念のため通常の出生前検査を「確認検査」として受けることが推奨されるのです。
見つけられる異常に限りがある
PGTで検査できる範囲にも限界があります。PGT-A/PGT-SRが対象とするのは主に染色体の数的・構造的な異常であり、例えばダウン症候群(21トリソミー)や重複転座など大きな異常にフォーカスしています。一方で、細かい遺伝子レベルの異常や後天的な変異、多因子疾患の発症リスクなどはPGTでは検出できません。一方でPGT-Mは遺伝子を見る検査ですが、特定疾患の変異だけを見るため、それ以外の予期しない異常はスルーされます。また、PGTでは胚の形態的な問題(着床力など)も評価できません。その結果、PGTで正常とされた胚でも出生時に何らかの疾患が見つかる可能性は残ります。例えば心臓の形態的な先天異常や、自閉症リスクといったものはPGTではわからないため、PGTを受けたからといって全ての先天的リスクを排除できるわけではない点に注意が必要です。過度な安心は禁物であり、PGT後も通常の妊婦健診でエコー検査などをきちんと受ける必要があります。
胚や親へのリスク・負担
PGT自体の身体的リスクは大きくありませんが、胚への微小なリスクは存在します。胚の生検操作や凍結・解凍によって、ごく僅かながら胚の生存率が低下する可能性が報告されています(胚盤胞生検による生存率98%→95%への低下など)。最新技術では影響は最小限とされていますが、胚操作が全く無害とは言い切れない点はデメリットです。また、親側への負担としてはホルモン刺激や採卵手術が必要になること、採卵・移植まで一連のスケジュール管理がタイトになること、精神的ストレスなどが挙げられます。
倫理的・社会的な問題
PGTには「命の選別」につながるとの倫理的指摘があります。胚の段階で選別・淘汰を行うことに対し、生命倫理の観点から慎重な議論がありました。日本産科婦人科学会も生命倫理に十分配慮した上で実施すべきとの声明を出しており、実際にPGTを受ける夫婦には事前に学会作成の啓発動画を視聴することが義務付けられています。また、PGTによって障害や疾患のある子どもの出生を排除することへの是非について社会的議論もあります。技術の進歩により将来的に検査で分かる範囲が広がれば、「どこまで選別を許容するのか」という問題が避けられません。
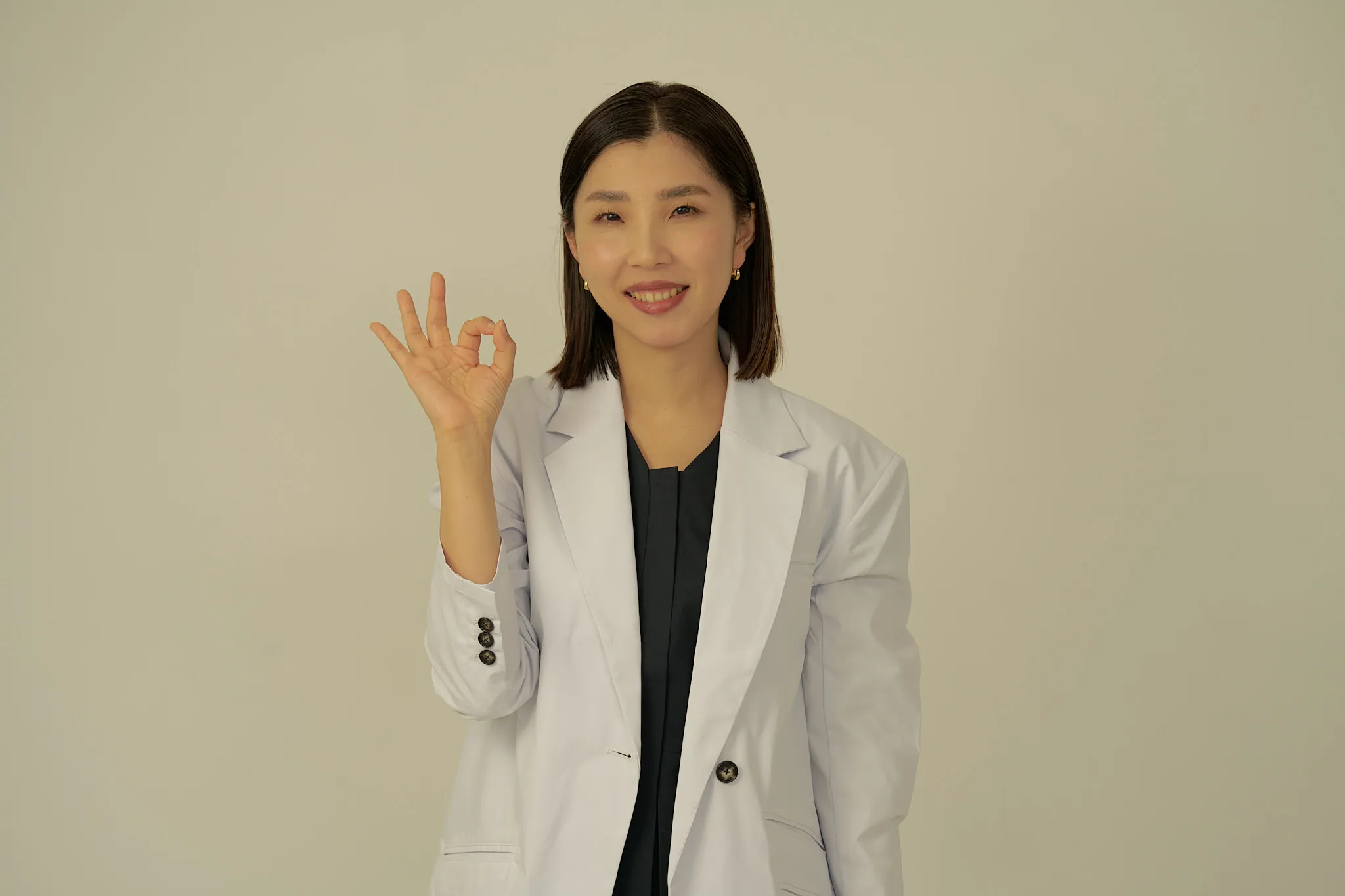
まとめると、「費用が高く誰もが受けられるわけではない」「検査も万能ではなく、完全な安心は得られない」という点がPGTの注意点と言えます。もちろんケースによってはデメリットよりメリットが大きく上回ります。必ずメリットとデメリットの両面を理解した上で判断することが大切です。
PGT?と出生前診断(NIPT等)との違い
着床前検査(PGT)と出生前診断(妊娠後に行う胎児の検査)には、検査のタイミングや対象、得られる情報が大きく異なるという違いがあります。両者はいずれも赤ちゃんの遺伝的な異常の有無を調べる点では共通していますが、PGTは妊娠が成立する前に受精卵を調べるのに対し、出生前診断は妊娠成立後の胎児を調べる点で対照的です。以下に、代表的な出生前診断である新型出生前診断(NIPT)などとの主要な違いを比較します。
| 項目 | 着床前検査(PGT) | 出生前診断(NIPT・羊水検査等) |
|---|---|---|
| 検査のタイミング | 妊娠成立前(胚移植前)に実施 | 妊娠成立後(妊娠10週以降)に実施 |
| 検査の対象 | 体外受精で得た受精卵(胚) | 胎児(妊娠中の赤ちゃん) |
| 検査方法 | 胚盤胞の栄養外胚葉から細胞を生検し、染色体や特定遺伝子を解析 | 母体から採血し血中胎児DNAを分析(NIPT)、または子宮に針を刺して羊水採取し胎児細胞を培養検査(羊水検査)など |
| 検査で分かる主な内容 | 胚の染色体異常や特定の遺伝子変異の有無(PGT-Aで全染色体の数的異常、PGT-SRで構造異常、PGT-Mで特定疾患の変異) | 胎児の染色体異常や一部先天疾患の可能性(NIPTでは13,18,21トリソミー等の確率を推定、羊水検査では胎児の全染色体検査や必要に応じて単一遺伝疾患の診断) |
| 検査結果の活用 | 移植する胚を選択する(異常が見つかった胚は子宮に戻さない) | 出産に向けた意思決定や準備に役立てる(異常が判明した場合、出生前に治療法がない重篤疾患であれば中絶を含めた選択を検討。また出産継続なら適切な医療準備) |
| 母体・胎児へのリスク | 母体への直接リスクはほぼなし(体外受精の過程による負担はあり)。胚へのリスクは僅かだが存在(胚生検・凍結による影響は最小限) | 流産リスクなど僅かにあり(NIPTは非侵襲的でリスクほぼ0、羊水検査は0.1〜0.3%程度流産リスク)※検査自体のリスクは低いが、異常指摘時の心理的負担大 |
| 検査の課題 | 技術・設備の整った専門施設でしか受けられない。費用が高額。検査精度に限界(モザイクなど)あり。倫理的課題(命の選別)あり。 | NIPTはスクリーニング検査であり確定診断ではないため偽陽性が出ることも(陽性的中率に限界あり)。陽性時は侵襲的検査(羊水検査等)での確定診断が必要。保険適用外で費用負担あり(NIPT約20万円、羊水検査数万円程度)。 |
PGTと出生前診断は競合するものではなく補完的な関係にあります。PGTは「異常胚を事前に排除して妊娠を成立させない」アプローチであり、一方出生前診断(NIPTや羊水検査等)は「妊娠成立後に胎児の状態を確認し、必要に応じて対応する」アプローチです。PGTを受けることで重篤な異常リスクを大きく減らすことはできますが、それでもすべての異常がゼロになるわけではないため、妊娠後も追加の確認として出生前診断を行う意義があります。実際、米国産婦人科学会(ACOG)など主要な産科ガイドラインでは「PGTを受けていても全ての妊婦に対して妊娠中の遺伝学的スクリーニング(NIPTなど)を提供すべき」と勧告しています。
PGTの費用・保険適用・助成金について
PGTの費用は前述の通り非常に高額です。改めて金額の目安を示すと、着床前検査にかかる費用は1サイクルあたり約50〜100万円が相場です。この費用には胚の遺伝子検査代だけでなく、生検の技術料なども含まれます。また体外受精自体の費用(採卵〜培養〜胚移植)も別途必要で、保険適用外で自費で行う場合は1回あたり数十万円かかります。PGTを希望する場合、多くのケースで保険適用外の自費治療となるた、1サイクルにトータル100万円以上の費用を見込んでおく必要があります。
ただし、2022年の不妊治療保険適用開始以降、体外受精の一部を保険で行いつつPGT部分のみ自費という形も可能になりました。具体的には、保険診療の体外受精と併用して先進医療(PGT)を受けた場合、体外受精部分は保険適用となり、PGT部分のみ自己負担となります。例えば採卵や培養費用は保険3割負担、PGT検査費用(例えば60万円)は全額自己負担という形です。
公的医療保険の適用状況
現時点(2025年時点)ではPGTは公的保険の適用外です。主な理由は、PGTで使用する遺伝子検査機器・試薬の一部が国内で薬事承認を得ていない先進技術であること、そして倫理面の慎重な検討が必要なことから、保険診療として一般化する段階にないためです。将来的にエビデンスが蓄積され社会的コンセンサスが得られれば保険収載も検討されるかもしれませんが、少なくとも数年以内の保険適用は見込まれていない状況です。したがってPGT関連費用は全額自己負担となり、高額医療費制度の対象にもなりません(※高額療養費は保険診療のみ対象)。
自治体の助成金制度
一部の自治体では、不妊治療の経済的負担軽減策としてPGTに対する助成金を設けています。例えば東京都では、PGT-Aを受けた場合に上限15万円まで助成を受けられる制度があります。これは東京都の特定不妊治療助成(先進医療分)として、不妊治療の保険診療と併用してPGT-Aを行った場合に適用されます。他にも神奈川県や大阪府など、独自にPGT費用の一部補助を行う自治体が増えてきています。助成の内容は自治体によって異なり、「PGT-Aのみ対象」「所得制限あり」「上限額○○万円まで」など条件があります。ご自身がお住まいの自治体にPGTに関する助成制度があるか、事前に各自治体の公式サイトや窓口で確認してみると良いでしょう。
PGT後のNIPTは必要?
米国の研究でも、PGT後に妊娠した約1100例を調査したところNIPTの陽性的中率(異常と出た場合に本当に異常である確率)が一般妊婦より低い(つまりPGTをすり抜けた異常は稀だが存在する)との結果が出ています。これは裏を返せば、PGT後であってもNIPTで異常が検出されるケースが皆無ではないことを意味します。幸いNIPTは母体血をとるだけでリスクはなく、費用面以外のデメリットはほぼありません。専門家は「PGTを受けていてもなお妊娠後はNIPTを全妊婦に提供すべき」との見解を示しており、例えばアメリカ産婦人科医会(ACOG)や日本産科婦人科学会もPGT後の妊婦への出生前診断実施を否定していません。
着床前診断(PGT)に関するよくある質問
着床前検査は保険はききますか?費用はどのくらいでしょうか?
PGTは公的医療保険が適用されず、全額自己負担になります。費用は施設や検査内容によって異なりますが、1回あたり50〜100万円前後が目安です。たとえばPGT-Aで胚5個を検査するケースでは70〜80万円程度、PGT-Mでは家系ごとの検査系開発費なども含め100万円を超えることもあります。体外受精の費用も含めると総額100万円以上を見込む必要があります。自治体によってはPGT費用の一部に助成金(例:東京都で最大15万円)が出る場合もありますので、住んでいる地域の制度を確認すると良いでしょう。
PGTを受けたいのですが、どこで受けられますか?
PGTは日本産科婦人科学会が認定した限られた施設でのみ実施されています(vol1の記事参照▶)。学会のホームページにPGT実施認定施設のリストがありますので参照してください。主に高度生殖医療を行っている不妊治療専門クリニックの中でも、遺伝カウンセリング体制が整い学会の臨床研究に参加している施設が対象です。お住まいの地域に実施施設がない場合、近隣の都市部の施設を紹介されることがあります。まずは今通院中の不妊治療クリニックでPGT対応可能か確認し、不可なら適切な施設を紹介してもらいましょう。
PGT後にも出生前診断(NIPTや羊水検査)は受けた方が良いですか?
はい、PGT後でも出生前診断を受けることが推奨されます。PGTで胚の主要な異常は除外できていますが、検査精度の限界からごく稀に見逃しがあり得るためです。ACOG(米国産婦人科医会)も「PGTで正常胚を移植した場合でも、妊娠後の遺伝スクリーニングは提供すべき」と勧告しています。NIPTは流産リスクもなく母体負担が少ない検査ですので、追加の安心材料として受けておく方が良いでしょう。もしNIPTで指摘があれば羊水検査で確認し、異常が否定されれば安心できますし、仮に異常確定でも早期に対応を検討できます。「PGTをしたからもう検査不要」と決めつけず、担当医と相談の上で出生前診断も前向きに検討することをおすすめします。。
PGTで正常な胚が一つも見つからなかった場合、どうなりますか?
残念ながらすべての胚に異常が見つかった場合、その採卵サイクルでは移植可能な胚がなく終了となります。高齢で卵子の質が低下している場合など、実際に起こり得る事態です。そうした場合、医師と相談して再度採卵を行いPGTを繰り返すか、配偶子提供(ドナー卵子/精子)の検討、あるいは治療自体の断念といった選択肢を考えることになります。非常に辛い結果ではありますが、ある意味では「妊娠しなかった理由が明確になった」とも言えます。次の一手を考える上で貴重な情報とも捉え、必要であればカウンセリング等のサポートを受けながら今後の方針を決めていきましょう。
PGTにはどんな倫理的問題がありますか?
PGTは胚の段階で選別を行うため、「命の選別」に当たるのではないかという倫理的懸念があります。重篤な異常を避ける目的とはいえ、将来生まれるはずだった命を淘汰することへの違和感を覚える方もいます。また、PGTが広がることで「障害や疾患のある子どもは生まれるべきでない」という風潮が強まるのではという指摘もあります。社会全体で見たときに優生思想につながらないか慎重な議論が必要です。ただ一方で、親子とも非常に過酷な運命を辿る可能性が高い疾患を事前に防ぐ意義も大きく、倫理と有用性のバランスをどうとるかが問われています。日本では学会がガイドラインで厳格に適応を限定し、実施前には必ず遺伝カウンセリングで倫理面も含め十分説明を行うことにしています。PGTを受ける際は夫婦でしっかり話し合い、納得の上で臨むことが大切です。
参考文献
日本産科婦人科学会「着床前遺伝学的検査に関する見解」(2022)
日本産科婦人科学会「PGT-Aに関する細則の改定について」(2025/9)

執筆者兼監修者プロフィール
東大産婦人科に入局後、長野県立こども病院、虎の門病院、関東労災病院、東京警察病院、東京都立豊島病院、東大病院など複数の病院勤務を経てレディースクリニックなみなみ院長に就任。
資格
- 医学博士
- 日本産科婦人科学会 産婦人科専門医
- FMF認定超音波医
…続きを見る
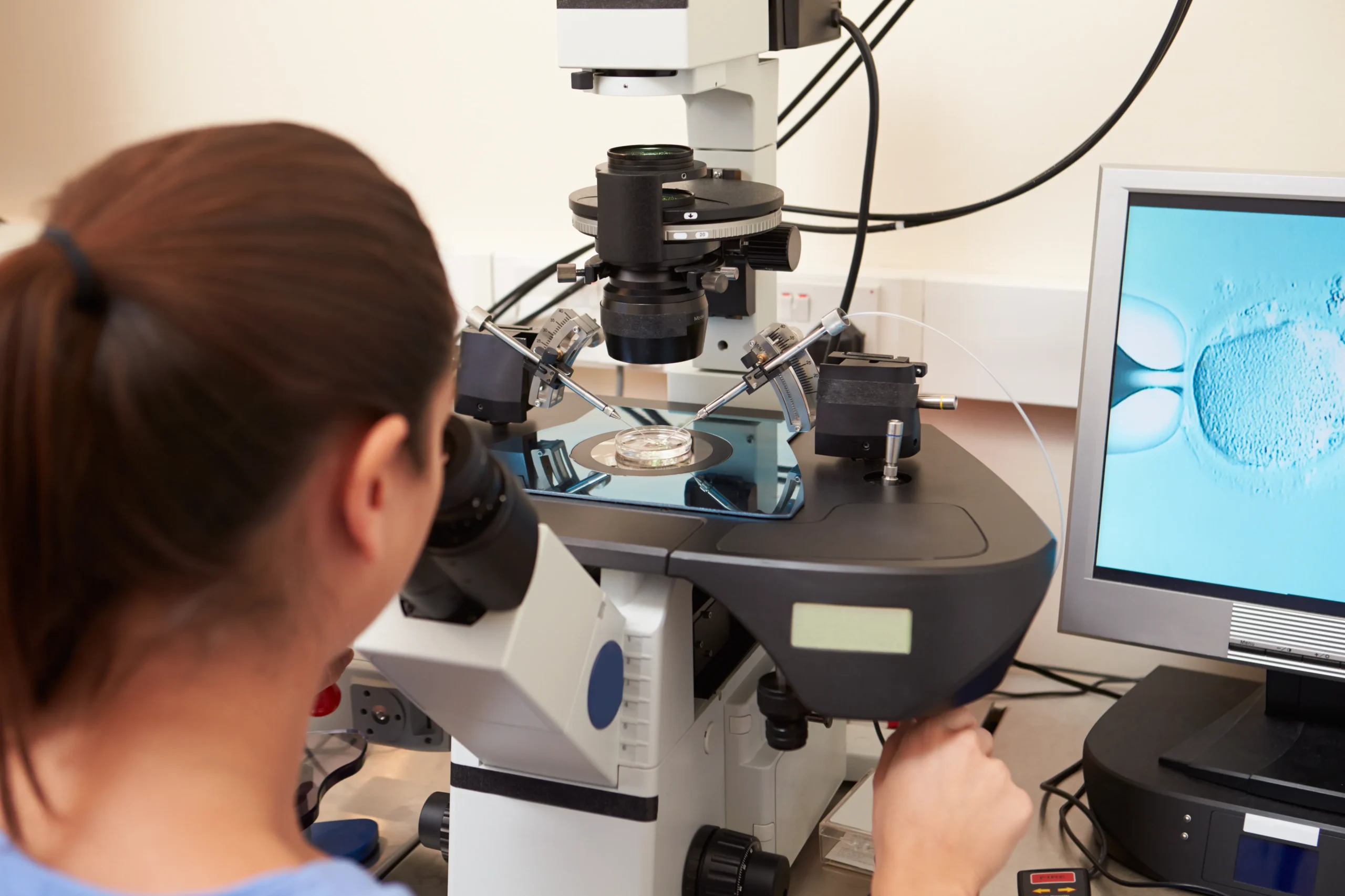

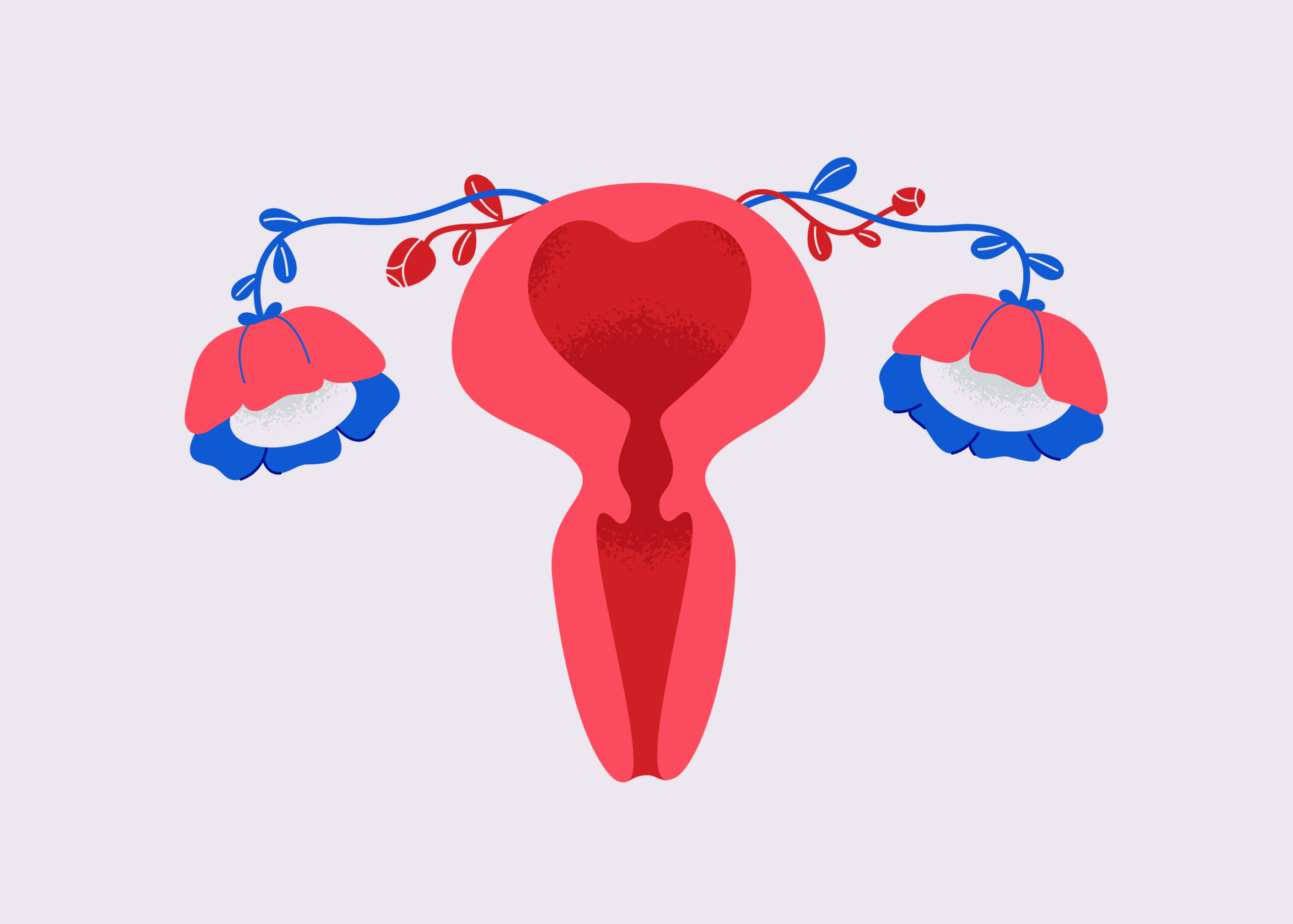











2025年9月にPGT-Aの適応が35歳上の女性に拡大され、今後PGTは間違いなく増えていく検査と言えます。vol1の記事ではPGTの基礎知識・種類・検査の流れ・対象者・メリットに関して説明しました。ここでは、デメリットや費用、注意点を説明します。