
執筆者兼監修者プロフィール
東大産婦人科に入局後、長野県立こども病院、虎の門病院、関東労災病院、東京警察病院、東京都立豊島病院、東大病院など複数の病院勤務を経てレディースクリニックなみなみ院長に就任。
資格
- 医学博士
- 日本産科婦人科学会 産婦人科専門医
- FMF認定超音波医
…続きを見る
着床前検査(PGT)とは、体外受精で得られた受精卵(胚)を子宮に戻す前に、胚の染色体や遺伝子に異常がないか調べる検査です。流産や着床失敗の原因となりうる異常胚の移植を避けることで、流産率の低下や妊娠成功率の向上が期待できます。
何度も流産や着床不成功を経験すると、「次こそは健康な胚を移植したい」と強く願う方も多いでしょう。着床前検査(PGT)はそんな願いをかなえる先進技術ですが、一方で費用や倫理面への不安、どんな人が受けられる検査なのか戸惑いもあるのではないでしょうか。ここでは以下を説明します。
この記事でわかること:
- 着床前検査(PGT)とは何か?その基本概要とPGT-A・PGT-SR・PGT-Mの3種類の違い
- PGTの検査の流れ(体外受精から胚の遺伝子検査、移植までの手順)
- PGTを受けられる対象者・適応条件
- PGTを利用するメリット(妊娠率向上・流産率低減など医学的な利点)
着床前検査(PGT)とは?
着床前検査(PGT: Preimplantation Genetic Testing)は、体外受精によって得られた受精卵を子宮に移植する前に、その胚の遺伝情報(染色体や特定の遺伝子)を検査する技術です。異常のない胚を選んで子宮に戻すことで、流産や先天異常のリスクを低減し、妊娠継続率を高めることを目的としています。日本では2004年に一部施設で臨床研究として開始され、倫理的配慮や高度な専門技術が必要なことから日本産科婦人科学会が認定した限られた施設でのみ実施されています。なおPGTはあくまで妊娠率向上や流産防止のための医療であり、男女の産み分け目的には利用できません(日本では医学的適応のない性別選択は認められていません)。
PGTの種類(PGT-A・PGT-SR・PGT-M)
PGT-A(胚の染色体数異数性検査)
胚の染色体数の異常(異数性)を調べる検査です。受精卵の染色体の本数に余分や欠如がある異常胚は、着床に失敗したり流産につながりやすいことが知られています。PGT-A(aneuploidy)では胚の染色体数を解析し、染色体数が正常な胚を選んで移植することで流産リスクの低減が期待できます。日本産科婦人科学会の定める適応条件では、体外受精による胚移植が2回以上うまくいかなかった不妊症カップル、あるいは2回以上の流産・死産を経験した不育症カップルがPGT-Aの主な対象です(ただし後述のPGT-SR対象となる染色体構造異常保因者を除きます)。一般的に高齢妊娠(35歳以上)では胚の染色体異常率が上昇し流産も増えるため、PGT-Aの有用性が高いと考えられています。例えば40歳代では染色体異常の確率、流産率が非常に高くなるため、PGT-Aで正常胚を見極めることが重要になります。
PGT-SR(胚の染色体構造異常の検査)
胚の染色体構造の異常(構造異常:欠失・転座など)を調べる検査です。夫婦のどちらかが「均衡型染色体転座」など染色体の構造異常を有している場合、受精卵に染色体の過不足(不均衡転座)が起き、流産・死産を繰り返す可能性があります。PGT-SR(structural rearrangement)では胚の染色体構造を解析し、不均衡転座のない胚を選んで移植することで流産や先天異常の発生を回避します。いずれかの配偶者に染色体構造異常(転座など)が確認されている不妊症・不育症の方が対象で、流産の回数に関係なく適応となります。PGT-SRによって染色体転座保因者でも健康な赤ちゃんを得られる可能性が高まります。
PGT-M(単一遺伝子異常の検査)
両親が特定の遺伝性疾患の原因遺伝子変異を保有している場合に、その変異の有無を胚単位で調べる検査です。例えば、親が重篤な遺伝性疾患(嚢胞性線維症や筋ジストロフィーなど)を子に伝える可能性があるケースでPGT-M(monogenic disorder)が検討されます。発症の原因となる特定の遺伝子変異を胚から検出し、その変異を持たない健常胚のみを選んで移植することで、子どもが当該疾患を発症することを防ぐことができます。日本産科婦人科学会では「成人前に生命に関わる深刻な症状が現れ、現時点で有効な治療法がない」疾患を「重篤な遺伝性疾患」と定義しており、そうした疾患のリスクがあるカップルがPGT-Mの対象となります。PGT-Mは一組一組のケースごとに学会の個別審査・承認が必要であり、限られた認定施設で遺伝専門医の指導のもと実施されます。
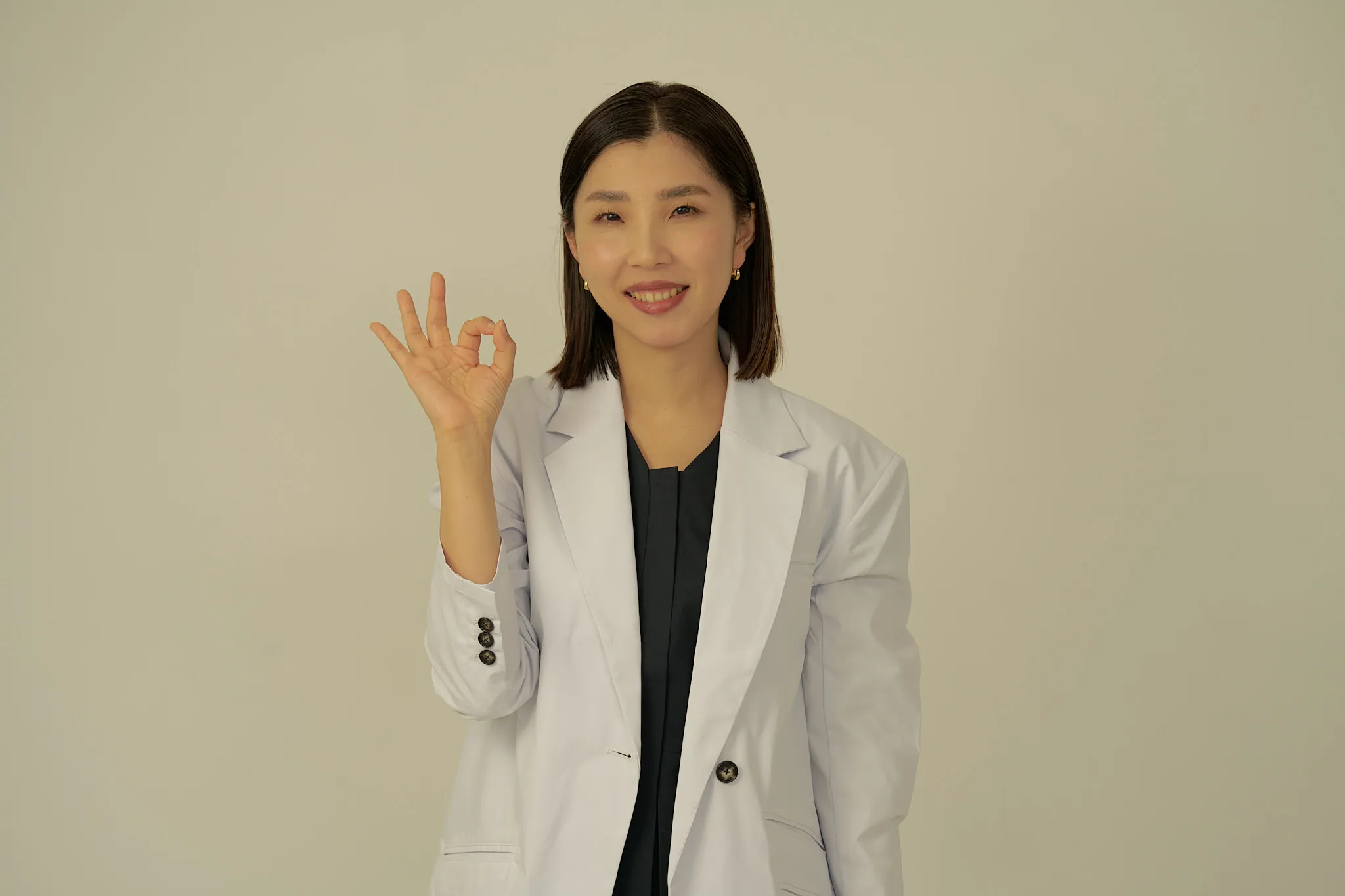
以上のようにPGTには目的に応じた3種類があります。それぞれ対象となる条件が厳密に定められており、検査の実施には事前に臨床遺伝専門医による遺伝カウンセリングが必須です。PGTを検討する場合は、自分たちの状況がどのPGTの適応に当てはまるか、専門医と十分に相談することが大切です。
検査の流れ(PGT実施のステップ)
PGTを受けるためには体外受精(IVF)の実施が前提となります。自然妊娠では胚を取り出して検査することはできないため、まず卵巣刺激・採卵によって複数の卵子を採取し、配偶者の精子と受精させて胚を育てる工程が必要です。以下にPGT実施までの一般的な流れを示します。
①遺伝カウンセリングと同意
まず夫婦で遺伝カウンセリングを受けます。PGTの意義や限界、リスクについて専門医から説明を受け、倫理的・社会的な側面も含めて十分に理解した上で書面同意します。特にPGT-Mの場合は対象疾患や検査法について学会の個別承認プロセスがあります。
②体外受精の実施
不妊治療専門クリニックにて体外受精を行います。卵巣刺激により複数の卵子を採取し、体外で精子と受精させて胚を培養します。得られた受精卵は培養5〜6日目に胚盤胞と呼ばれる100細胞程度に成長します。この時点でPGTに必要な検体を得るため顕微鏡下で胚の一部を生検(バイオプシー)します。
③胚の生検(胚盤胞生検)
胚盤胞の将来胎盤になる部分(栄養外胚葉)から5〜10個ほどの細胞を採取します。この操作により将来赤ちゃん本体になる内部細胞塊には手を触れないため、胚を傷つけるリスクは極めて低く抑えられています。採取した細胞は分析用に送ります。一方、生検後の胚自体は凍結保存されます(胚凍結)。生検結果が出るまで胚を凍結して待機することで、検査結果を確認してから安全な胚移植を行うことができます。
④遺伝学的検査(PGT解析)
生検で得た胚細胞からDNAを増幅し、遺伝学的解析を行います。解析手法は検査の種類によって異なります。PGT-A/PGT-SRでは次世代シーケンサー(NGS)やマイクロアレイを用いて胚の全染色体を網羅的に分析し、数的異常や構造異常を判定します。PGT-Mでは対象疾患の原因遺伝子変異に絞った遺伝子検査(PCR法やシーケンス法等)を行います。検査には数日~数週間程度を要します。結果の精度を確保するため、各検体は複数回検査され、必要に応じて家系の遺伝子情報と照合されます。
⑤結果の説明と胚選択
検査結果に基づき、それぞれの胚の状態が「移植に適した正常範囲内」か「異常が検出されたため移植不適」であるかが判定されます。医師や遺伝カウンセラーから結果の詳細な説明を受け、移植可能な胚が存在する場合はどの胚を移植するか相談して決定します。異常が判明した胚については原則として子宮に戻しません(多くの施設では廃棄もしくは研究利用への同意を得て保管となります)。複数の正常胚が得られた場合は、グレード(形態評価)や夫婦の希望を踏まえて移植胚を選択します。

以上がPGT実施までの大まかな流れです。PGTには高度な技術と専門的判断が伴うため、実施できる施設は限られています。日本産科婦人科学会の臨床研究に参加している生殖医療施設や、PGT-M症例ごとに認可を受けた施設でのみ行われます。PGTを希望する場合は、主治医に相談し適切な施設への紹介を受けるとよいでしょう(日本産科婦人科学会のホームページでPGT実施施設を検索することもできます▶こちらから)。
対象となる人(PGTが受けられる条件)
着床前検査PGTは誰もが自由に受けられる検査ではなく、日本では学会が定めた明確な適応条件を満たす場合にのみ行われます。基本的に体外受精を行っている不妊治療中のカップルが対象であり、自然妊娠の方や不妊治療中でも適応条件に該当しない方はPGTを受けることができません。
PGT-Aの適応
前述の通り、反復着床不全(体外受精による胚移植が2回以上不成功)または反復流産(2回以上の流産または死産)の既往があるご夫婦が対象です。ただし夫婦のどちらかに染色体の構造異常がある場合(転座保因者など)はPGT-AではなくPGT-SRの適応となります。なお、PGT-Aは胚盤胞まで育った胚が得られることが前提です。胚盤胞まで発育しないケースや、明らかに若年で胚異常の確率が低いケース(例えば35歳未満でその他不妊要因が明確な場合)は、PGT-Aの有用性が低いため適応外となることがあります。
PGT−Aの適応について
2025年からPGT-Aの適応についての細則が変更になり、女性が35歳以上の不妊症の夫婦にも適応が広がりました(従来は不妊治療を繰り返しても妊娠しない場合や流産の経験を持つ場合に限っていました)。女性の年齢が35歳を境にPGT-Aを施行したほうが妊娠率が改善する報告が出ているためです。
PGT-SRの適応
不妊症または不育症の夫婦のうちどちらかが染色体構造異常(例:均衡型転座)を有する場合が対象です。この条件に該当すれば流産歴の有無に関係なく適応となります。PGT-SRを行うことで、不均衡転座に起因する流産や胎児の重篤異常を避けることができます。夫婦のいずれかが過去に出生したお子さんで染色体異常が判明している場合なども含め、該当する場合は積極的に検討されます。
PGT-Mの適応
特定の重篤な遺伝性疾患の素因があるカップルが対象です。具体的には、夫婦のどちらかが遺伝性疾患の原因となる遺伝子変異や構造異常を保有しており、それが子に50%の確率で遺伝する(常染色体優性遺伝やX連鎖遺伝など)場合が典型です。過去にその疾患をもつお子さんを亡くされた、あるいは家族歴があるケースが想定されます。対象疾患は学会のガイドラインで定義された「重篤な遺伝性疾患」に限られます(例:乳児期に致死的な神経変性疾患など治療法がないもの)。PGT-Mは症例ごとに日本産科婦人科学会の審査承認が必要なため、まず主治医を通じて適応となるか検討・申請し、許可が下りた場合にのみ実施されます。審査にあたっては疾患の重篤性や家系背景、他の選択肢の有無などが考慮されます。
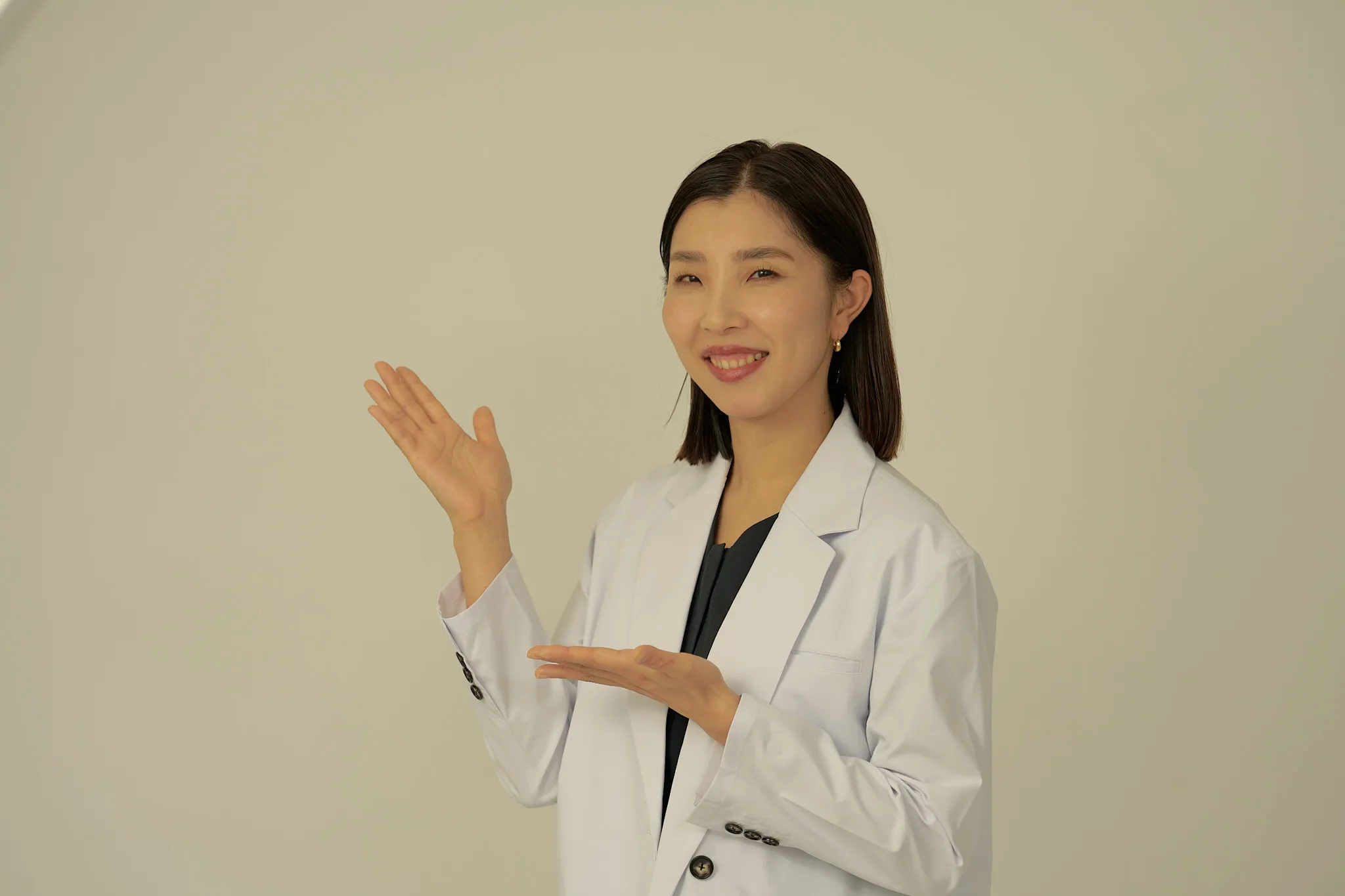
以上が主なPGTの対象者です。要約すれば、「原因不明の胚異常による不妊・不育に悩む方」や「親から子への遺伝疾患リスクに直面している方」がPGT適応となります。逆に言えば、明確な適応理由がなければPGTは受けられません。特にPGT-Aに関しては現在日本では学会管理下の臨床研究扱いであり、「とりあえず不安だから調べたい」という希望だけでは行えない点に留意しましょう。適応条件を満たすかどうか判断が難しい場合は、不妊治療主治医や遺伝カウンセラーに相談するとよいでしょう。
PGTのメリット
着床前検査PGTには、適応となるケースにおいてさまざまなメリットが期待されています。ここでは主なメリットを順に説明します。
流産率の低下
PGT最大の利点の一つが流産リスクを減らせることです。特にPGT-Aでは染色体数異常のない胚を選ぶため、染色体異常が原因で起こる流産を大幅に防ぐ効果が期待できます。流産の約半数以上は胚の染色体異常によるものとされ、これは高齢になるほど頻度が増します。PGT-Aによってこうした異常胚の移植を避けられれば、妊娠しても流産に至るケースを減らすことが可能です。実際、35歳以上の高齢不妊ではPGT-Aを併用することで流産率が有意に低下したとの研究報告もあります。何度も流産を経験しているカップルにとって、流産の不安が軽減されることは大きな精神的メリットといえるでしょう。
妊娠率・出産率の向上
PGTは胚移植あたりの妊娠成功率を高める可能性があります。正常と判定された胚のみを移植するため、着床せず無駄に終わる移植を減らし、1回の移植で妊娠に至る確率を上げる効果が期待できます。特にPGT-Aは高齢女性で有効とされ、あるメタ解析では35歳以上の女性ではPGT-Aを行った群のほうが出産成功率が有意に高かったとの結果が報告されています。一方、35歳未満では有意差がなかったとの報告もあり、妊娠率向上効果は年齢や胚数によって異なる可能性があります。しかし総じて、胚あたりの妊娠効率を上げることで治療全体の期間短縮や費用対効果の向上が期待できます。実際、欧米の施設ではPGT-Aを用いて選別した単一胚移植を行うことで多胎妊娠を回避しつつ高い妊娠率を維持している例もあります(選別した胚を1個移植するだけで高確率で妊娠するため、不要な複数移植を避けられる)。このようにPGTは着床率・出産率の向上に寄与しうる技術です。
遺伝性疾患の回避
PGT-Mの活用により、お腹の赤ちゃんが重い遺伝病を持つリスクを事前に排除できます。親から子へ50%の確率で遺伝するような重篤疾患(例:筋萎縮性側索硬化症の家系など)では、従来は自然妊娠後に出生前診断や産前検査で判明しても中絶以外に防ぐ手立てがありませんでした。PGT-Mを使えば病気の原因となる変異を持たない受精卵だけを選んで移植できるため、健常な子どもを得られる可能性が飛躍的に高まります。これは家系の遺伝病で苦しんできた夫婦にとって大きな恩恵です。また、PGT-SRも含めて出生前(妊娠成立前)の段階でリスクを取り除けるため、妊娠後に「産むか中絶か」という辛い決断を避けられるメリットもあります。安心して妊娠・出産に臨める心理的メリットは計り知れません。
反復不成功への突破口となる
原因不明の反復着床不全や流産反復に直面しているケースでは、PGTが最後の切り札となることがあります。胚の見た目(形態評価)では分からない異常をPGTで発見できれば、問題のある胚を避けて移植計画を立て直すことができます。実際にPGTを行った結果、今まで一度も陽性にならなかった方が初めて妊娠継続できたという報告もあります。特に年齢要因以外に明確な不育症の原因がない場合、胚側の染色体異常が隠れた原因である可能性が高く、PGT-Aによる選別が有効と考えられます。このようにPGTは、従来打つ手がなかった難治性不妊・不育に対して新たな活路を提供するメリットがあります。
精神的・肉体的負担の軽減
繰り返す流産や体外受精失敗は、夫婦にとって大きなストレスと身体的負担になります。PGTの活用で無駄な移植や流産を減らせれば、治療に伴う心身の負担軽減にもつながります。正常胚が得られなかった場合は早期に次の方針(例えば提供卵子の検討など)に切り替えられるため、ズルズルと不成功を重ねるよりトータルの負担が少なくなる場合もあります。また、PGTを行うことで「できる限りのことはした」という安心感を持って妊娠に臨める点も見逃せません。妊娠中の不安を少しでも減らし、前向きな気持ちで過ごせることは母体の健康にも良い影響を与えるでしょう。
以上がPGTの主なメリットです。ただしvol2に述べるように、PGTにはデメリットや限界も存在します。メリットとデメリットの両面を正しく理解した上で、PGTを受けるかどうか検討することが重要です。
レディースクリニックなみなみを予約する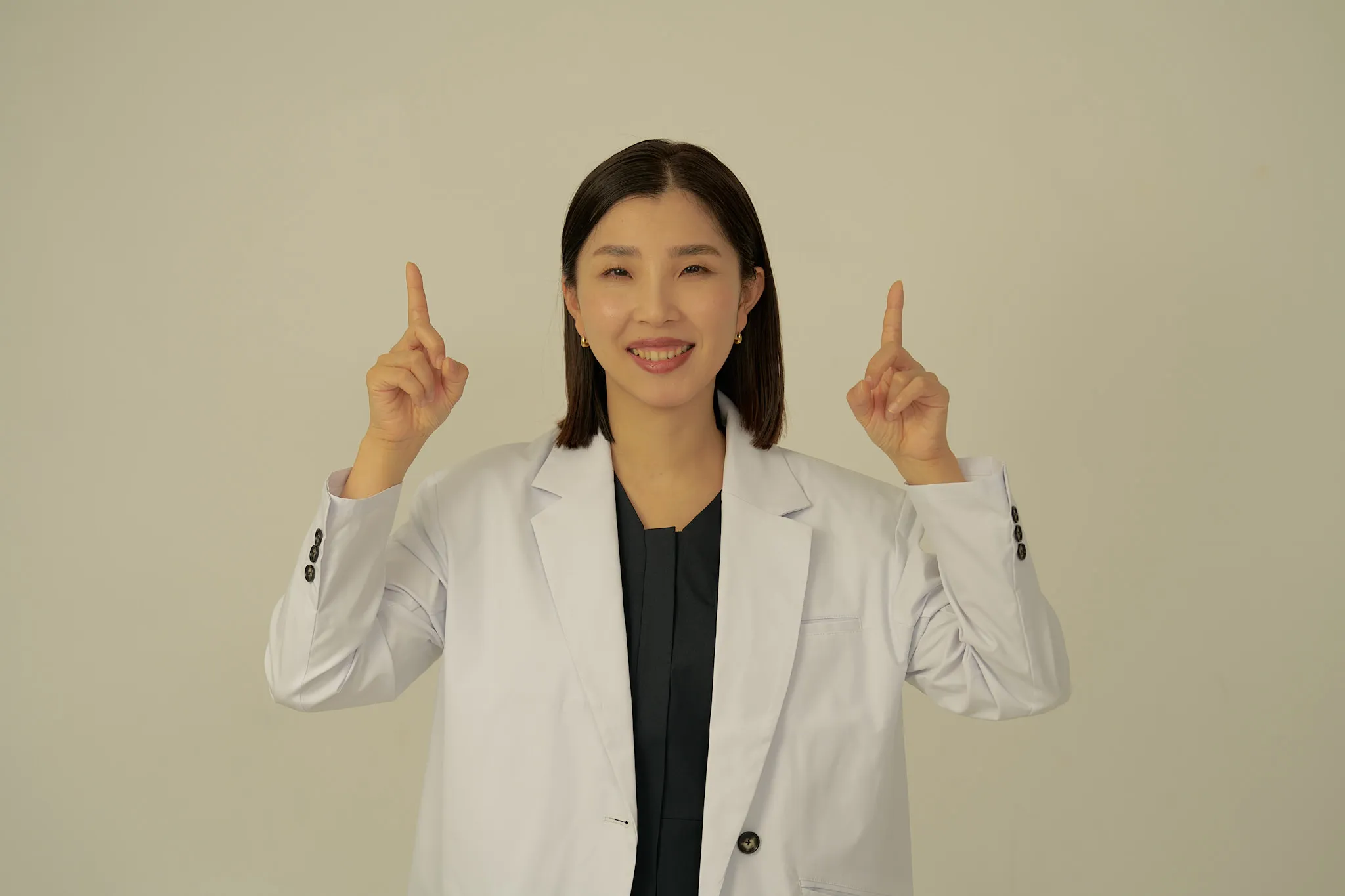
今回の記事では検査の種類・流れ・対象者・メリットについて解説しました。
着床前検査のデメリット・NIPTとの違い・費用・注意点に関してはこちらの記事▶で詳しく説明しています。気になっている方はぜひ御覧ください。
着床前】診断(PGT)に関するよくある質問
従来言われていた「着床前診断(PGD)」とPGTは同じものですか?
はい、基本的には同じ概念です。以前は特に遺伝性疾患を対象としたものを「着床前診断(PGD)」、染色体数異常のスクリーニングを「PGS」と呼んでいました。2017年に国際的な用語整理が行われ、これらを含めた総称としてPGT(Preimplantation Genetic Testing)という呼び名に統一されています。現在、日本産科婦人科学会でもPGT-A/SR/Mという区分で呼称しており、旧来のPGD/PGSもPGTに含まれると考えてよいでしょう。
PGTは誰でも受けられるのでしょうか?
いいえ、PGTは適応条件を満たす場合に限り行われます。PGTを実施するには日本産科婦人科学会の定める条件(流産や不妊の反復、特定の遺伝疾患のリスクなど)に該当し、かつ学会認定施設での遺伝カウンセリング受診と同意取得が必要です。したがって「とりあえず不安だから調べたい」という理由では受けられず、例えば高齢で体外受精がうまくいかない場合や家系的に重い遺伝病の不安がある場合など、医学的に妥当と判断されたケースのみPGTが行われます。まずは主治医に自分たちがPGT適応か相談し、必要なら専門施設を紹介してもらいましょう。
PGTで胚の性別は分かりますか?また、男女の産み分けに利用できますか?
胚の性別染色体自体はPGT-Aの結果から判明し得ますが、産み分け目的でその情報を利用することは禁止されています。PGTの目的はあくまで染色体異常や遺伝病の有無を調べることであり、日本では医学的理由なく性別で移植胚を選別することは認められていません。仮に結果として性別が分かる場合でも、通常カップルへは伝えられず、医療者側で適切な胚を選んで移植します。また、特定の遺伝病(例:X連鎖遺伝疾患)を避けるために性別情報を利用することは稀にありますが(この場合も学会審査が必要)、希望する性別の子どもを得るためにPGTを受けることはできません。
PGTを受ければ必ず妊娠できますか?
PGTを受けても必ず妊娠・出産できるとは限りません。PGTは流産や移植失敗を減らすのに有用ですが、妊娠そのものを保証するものではない点に注意が必要です。正常胚を選んでも子宮側の要因などで着床しないこともありますし、胚自体が健康でも妊娠合併症など他の問題が起こる可能性もあります。また高齢で卵子の質自体が低下している場合、PGTで正常胚が得られない(移植できる胚がない)こともあります。PGTはあくまで確率を上げる手段であり、100%の成功を保証するものではないと理解しておきましょう。
胚の一部を切り取って検査するとのことですが、そのことで生まれてくる赤ちゃんに影響はありませんか?
現時点の研究では、胚盤胞期の生検による赤ちゃんへの有害な影響は認められていません。PGTでは胚のうち将来胎児にならない部分(胎盤になる細胞)から数個を採取します。赤ちゃん本体になる細胞には触れないため、生まれた赤ちゃんの発育に影響しないと考えられています。実際、PGTが始まって約30年経ちますが、PGT児に特有の健康問題は報告されていません。ただしPGT自体歴史の浅い技術のため、「長期的な影響は完全には分かっていない」という慎重な見解もあります。現状では大きなリスクはないと考えられますが、不安な場合は遺伝カウンセリングで最新の知見について説明を受けると良いでしょう。
参考文献
日本産科婦人科学会「着床前遺伝学的検査に関する見解」(2022)

執筆者兼監修者プロフィール
東大産婦人科に入局後、長野県立こども病院、虎の門病院、関東労災病院、東京警察病院、東京都立豊島病院、東大病院など複数の病院勤務を経てレディースクリニックなみなみ院長に就任。
資格
- 医学博士
- 日本産科婦人科学会 産婦人科専門医
- FMF認定超音波医
…続きを見る

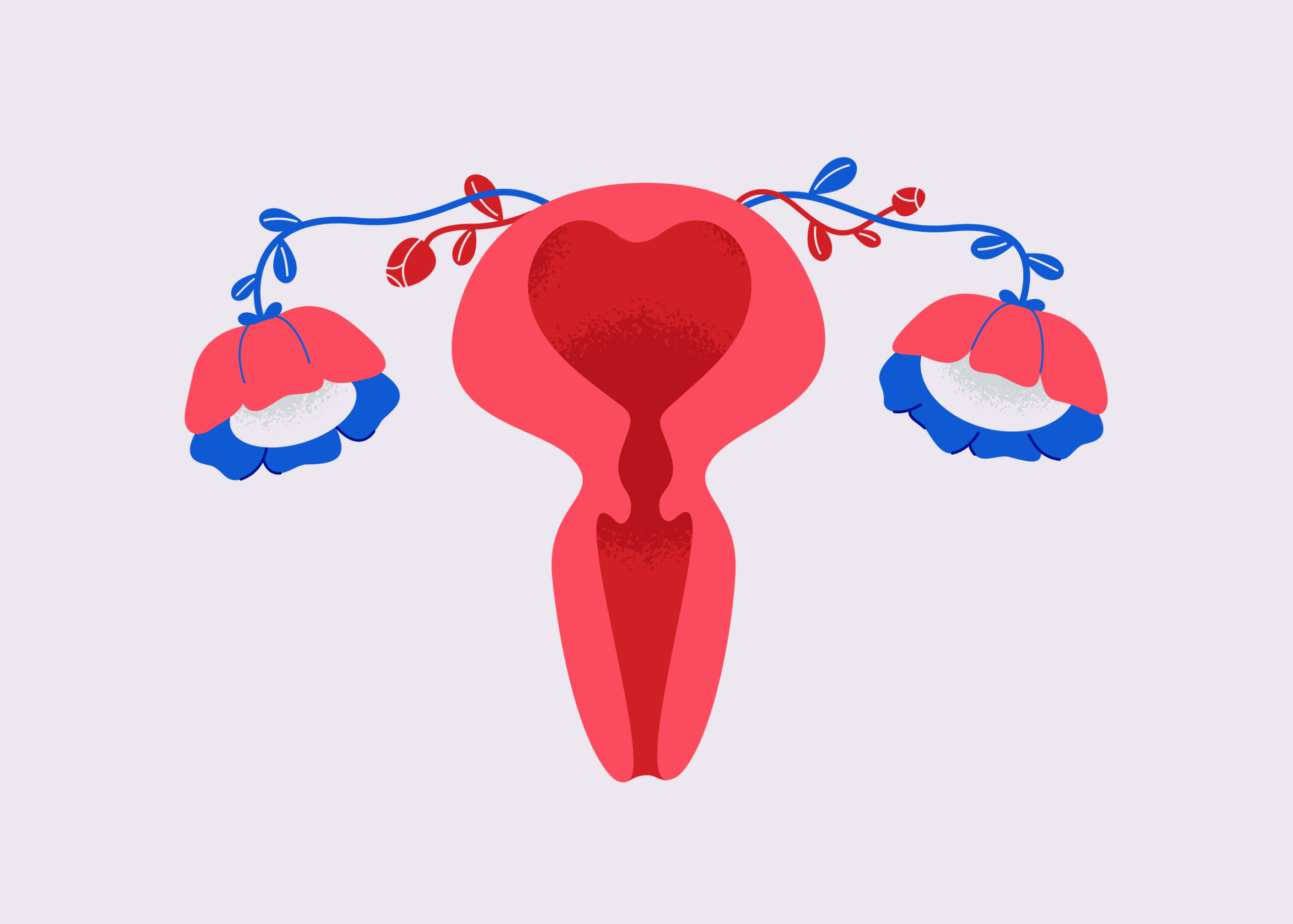












近年、従来「着床前診断(PGD)」や「着床前スクリーニング(PGS)」と呼ばれていたものが国際的にPGTという用語に統一されました。PGTは検査の目的や対象に応じて3つの種類に分類されます。以下ではPGT-A・PGT-SR・PGT-M各検査の目的と対象について解説します。