
執筆者兼監修者プロフィール
東大産婦人科に入局後、長野県立こども病院、虎の門病院、関東労災病院、東京警察病院、東京都立豊島病院、東大病院など複数の病院勤務を経てレディースクリニックなみなみ院長に就任。
資格
- 医学博士
- 日本産科婦人科学会 産婦人科専門医
- FMF認定超音波医
…続きを見る
妊活とは、赤ちゃんを望む夫婦が妊娠に向けて行うあらゆる活動の総称です。妊娠にはタイムリミットがあるため、妊活は早めに始め、必要に応じて適切なタイミングで医療の力を借りることが大切です。とはいえ、いざ始めようとすると「何から始めればいいの?」「まだ早い?それとも遅い?」など不安になる方も多いでしょう。実際、現在は6組に1組の夫婦が不妊検査や治療を経験する時代ともいわれており、妊活に悩むのは珍しいことではありません。大切なのはお二人で協力し合い、正しい知識とステップで一歩ずつ進めることです。
本記事では、これから妊活を始める人に向けて妊活の基本から不妊治療との違い、始めどきや自宅でできる取り組み、妊娠しやすい体づくりのポイント、パートナーにできるサポート、クリニック受診の目安までやさしく解説します。専門的な内容も含みますが、できるだけわかりやすくまとめましたので、安心して読み進めてくださいね。最後にはよくある質問(FAQ)にもお答えします。
妊活の定義:妊娠を望むすべての行動
「妊活(にんかつ)」とは「妊娠活動」の略で、妊娠・出産に向けて行うあらゆる前向きな活動を指します。明確な医学上の定義があるわけではありませんが、一般的には次のようなものが妊活に含まれます。
- 妊娠・出産について夫婦で話し合うこと:将来の家族計画や仕事との両立などについて意見交換し、計画を共有します。
- 妊娠に関する正しい知識を身につけること:排卵や受精の仕組み、年齢と妊娠率の関係、必要な栄養素などを学びます。
- 妊娠しやすい体づくりをすること:後述するような生活習慣の改善(食事・運動・睡眠・禁煙など)で健康管理に努めます。
- 排卵日を予測しタイミングよく性交すること:基礎体温や排卵検査薬などで妊娠しやすいタイミングを見極め、夫婦生活の頻度とタイミングを工夫します。
- 必要に応じて不妊治療を受けること:一定期間妊娠しなければ、医療機関で検査・治療を開始することも妊活の一環です。
このように妊活は女性だけでなく男性も含めた二人三脚の取り組みです。妊娠には卵子と精子の出会いが不可欠で、不妊の原因は約半数が男性側にあるという調査結果もあります(世界保健機関<WHO>の報告によれば、不妊に悩むカップルの約50%で男性にも原因が認められています)。したがって、「妊活=女性が頑張るもの」では決してありません。お二人で協力し合うことが何より大切なのです。
また、近年は晩婚化や共働きなど生活環境の変化により、望んでもすぐに妊娠できないケースが増えています。1980年には26歳前後だった第一子出産時の母親平均年齢は、現在30歳を超えています。当然ながら加齢とともに妊娠のしやすさは低下するため、計画的な妊活への関心が高まっているのです。「避妊をやめればすぐに赤ちゃんができるはず」と考えがちですが、健康な夫婦でも排卵のタイミングを狙って性交して妊娠する確率は1周期あたり25~30%程度とされています。すべてのカップルがすんなり妊娠できるわけではないため、意識的に妊娠を目指す「妊活」が必要になってくる背景があります。
妊活と不妊治療はどう違うの?
妊活と不妊治療は目的は共通していますが、指す範囲とアプローチが異なります。妊活が上で述べたように妊娠に向けたあらゆる自主的な活動を含む広い概念であるのに対し、不妊治療は医療機関で行う専門的な治療行為を指します。
妊活
まずは基礎体温の測定や生活習慣の見直し、排卵日に合わせたタイミング法(性交の時期調整)など、自宅でできる取り組みから始めます。必要に応じてブライダルチェック(妊活検査)を受けたり、産婦人科でアドバイスを受けることも含まれます。妊活には明確な「これをすれば正解」というステップがあるわけではなく、各ご夫婦の状況に合わせた柔軟な方針となります。例えば、年齢や持病、仕事や家庭の事情によって妊活の進め方や期間は人それぞれです。
不妊治療
一定期間妊活を続けても妊娠に至らない場合に医療の力を借りるステップです。不妊症と診断された場合、治療には一般的な進め方が存在します。まずタイミング法(医師の指導のもと排卵日に合わせて性交する方法)を数周期試み、それでも妊娠しなければ人工授精(AIH)へ進みます。人工授精とは、採取した精液を子宮内に直接注入して受精を促す方法です。さらに必要なら体外受精(IVF)や顕微授精(ICSI)など高度生殖補助医療へとステップアップしていきます。不妊治療ではこのように治療内容・段階が明確に体系化されています。一方で、どの治療を選ぶかは不妊の原因や年齢によっても異なります。例えば女性が35歳以上の場合、時間を優先して初めから人工授精や体外受精など積極的な治療から開始するケースもあります。いずれにせよ、不妊治療は医師による検査結果を踏まえた適切な方法の選択と実施が伴います。
まとめると、妊活は「妊娠に向けた準備・行動」全般を指し、その中には不妊治療も含まれうるという位置づけです。妊活の延長線上に不妊治療があるイメージで捉えるとよいでしょう。「妊活=自分たちで頑張ること」、「不妊治療=お医者さんの力を借りること」と考えると違いがわかりやすいかもしれません。ただし実際には境界ははっきり線引きできるものではなく、妊活を進めていく中で必要に応じて不妊治療へ移行していく形になります。重要なのは、「いつ専門的な治療に切り替えるか」を見極めることです。それについては後述する「クリニック受診の目安」の項目で詳しく説明します。
妊活を始めるタイミングはいつがいい?
「妊活は早いほうがいい」とよく言われますが、実際はパートナーと「赤ちゃんが欲しい」という気持ちが固まったときが始めどきです。妊活は夫婦で協力して行うものですから、まずはお互いの意思が一致していることが前提となります。そのうえで、一般的にはできるだけ早めにスタートすることをおすすめします。
年齢と妊娠率の関係
妊娠のしやすさは女性・男性ともに年齢とともに低下します。女性の場合、卵子の数と質が加齢で徐々に衰えていくため、医学的に妊娠・出産に適した時期は20代~30代前半とされています。実際、女性が35歳を過ぎると自然妊娠の確率は下がり始め、流産率や出生時のリスクも上昇していきます(日本産科婦人科学会では35歳以上の初産婦を「高齢出産」と定義しています)。男性も同様に加齢で精子の運動率や質が低下する可能性が報告されています。
ただし現代では35歳以降で出産する方も珍しくありませんし、40代で妊娠する例もあります。年齢が全てではありませんが、「妊娠にはタイムリミットがある」という事実は心に留めておきましょう。「いつか欲しい」と考えている段階でも、早めにパートナーと話し合い計画を立てることで、後悔のないタイミングで妊活を始めることができます。
妊活開始の目安と夫婦の話し合い
具体的に「結婚して○年経ったら」「○歳になったら」という決まりはありませんが、先輩カップルのアンケートでは「結婚後1年以内に子どもが欲しい」と考える人が約40%、2~3年以内では約48%という結果もあります。多くの夫婦が結婚して比較的早い段階で子どもを望む傾向にあります。お二人の年齢やライフプラン(仕事や経済面)、健康状態などを考慮し、「そろそろかな」と思った時が始めどきです。
とはいえ、夫婦で温度差がある場合もあるでしょう。その際は無理に急かすのではなく、お互いの希望や不安をじっくり話し合うことが大切です。妊活は一人ではできませんから、二人の気持ちが揃ったタイミングでスタートするのがベストです。
もしパートナーが妊活に前向きでない場合は、焦らずに妊活セミナーや産婦人科の相談外来などを活用して、一緒に情報収集してみるのもよいでしょう。最近は自治体や病院で夫婦向けの妊活セミナーが開催されていたり、妊娠・不妊に関する知識を学べるパンフレットなども充実しています。専門家の話を聞くことで男性側の理解が深まり、協力的になってくれるケースもあります。
自宅でできる妊活ステップ
妊活を始めたら、まずは自宅でできる基本的なステップに取り組んでみましょう。病院に行く前にできる工夫はたくさんあります。ここでは主なポイントを順番に説明します。
1. 生理周期を把握し排卵日を予測する
排卵日の前後は最も妊娠しやすいタイミングです。卵子と精子が出会うにはタイミングが重要ですから、まずはご自身の生理周期を正確に知りましょう。具体的な方法は次の通りです。
基礎体温を測る
朝目覚めたときに基礎体温計で舌下体温を測定し、毎日記録します。排卵が近づくと女性ホルモンの変化で体温がわずかに下がり、排卵後は黄体ホルモンの作用で体温が高い状態(高温期)に移行します。低温期から高温期へ切り替わるタイミングがおおよその排卵日と考えられます。基礎体温表をつけ続けることで、自分の排卵パターンやリズムがつかめてきます。最近ではスマホのアプリに体温を入力すると自動でグラフ化し、排卵日予測までしてくれる便利なものもあります。
排卵検査薬を使う
ドラッグストア等で購入できる排卵日検査薬(排卵予測キット)も活用しましょう。尿中のホルモン値を調べて排卵の兆候を捉える検査薬で、陽性反応が出たら「24~36時間以内に排卵の可能性が高い」ことを示します。生理周期に合わせて数日前から毎日検査し、反応を確認します。排卵検査薬を使うと排卵日がより正確に予測でき、妊活のタイミングを取りやすくなります。
生理管理アプリで記録する
月経開始日と終了日を記録しておくだけでも排卵日の目安を予測できます。生理周期が安定していれば、次回生理予定日の約14日前が排卵日です。アプリには体調メモやパートナーと情報共有できる機能があるものもあり、妊活の強い味方になります。
2. 排卵日前後にタイミングよく夫婦生活をもつ
排卵日がわかったら、その前後の数日間に集中的に夫婦生活(性交渉)をもつよう心がけましょう。特に排卵日の2日前くらいがもっとも妊娠しやすいタイミングとされています。卵子の寿命は排卵後約1日ですが、精子は射精後3日ほど生存すると言われます。つまり排卵の少し前からタイミングを取っておくことで、排卵の瞬間に受精可能な精子が女性の体内にいる状態を作ることができます。具体的には、「排卵日予測の2日前から当日まで」に1~2日おき程度の性交が望ましいでしょう。
なお、プレッシャーに感じる必要はありませんが、「妊娠のため」と意識しすぎて夫婦生活が義務的になってしまうケースもあります。ストレスを溜めないよう、お二人でリラックスできる雰囲気作りも大切です。難しい場合は無理に排卵日ぴったりを狙いすぎず、週に2~3回程度のペースでコンスタントに仲良くしていれば十分妊娠のチャンスはあります。精子は毎日よりも1~2日おきの射精の方が質が良いとも言われますので、適度な頻度を維持しましょう。
3. 生活習慣を見直し妊娠しやすい環境づくり
妊活中はぜひ普段の生活習慣も妊娠を意識したものに整えていきましょう。次の章「妊娠しやすい体づくり」で詳しく述べますが、食事・睡眠・運動など基本的な生活の質を上げることが、結果的に妊娠率アップにつながります。例えば以下のような点に注意してみてください。
栄養バランスの良い食事
妊活中は女性も男性も栄養状態が重要です。特に葉酸(後述)、鉄分、亜鉛、ビタミン類、良質なたんぱく質を意識して摂り、加工食品やジャンクフードは控えめに。毎日3食規則正しく食べましょう。
適度な運動
ウォーキングや軽いジョギング、ヨガなど無理のない範囲で体を動かし、血行を促進します。肥満や運動不足はホルモンバランスにも悪影響を及ぼすので要注意です。
禁煙・節酒
喫煙は女性の卵巣機能低下や男性の精子数減少につながるため妊活中は禁煙が望ましいです。また大量の飲酒も避け、飲むとしても適量に留めましょう。
十分な睡眠とストレスケア
睡眠不足や過度なストレスはホルモンの分泌リズムを乱す原因になります。夜更かしを避けて7時間前後の睡眠を確保し、リラックスできる時間を設けるよう意識してください。
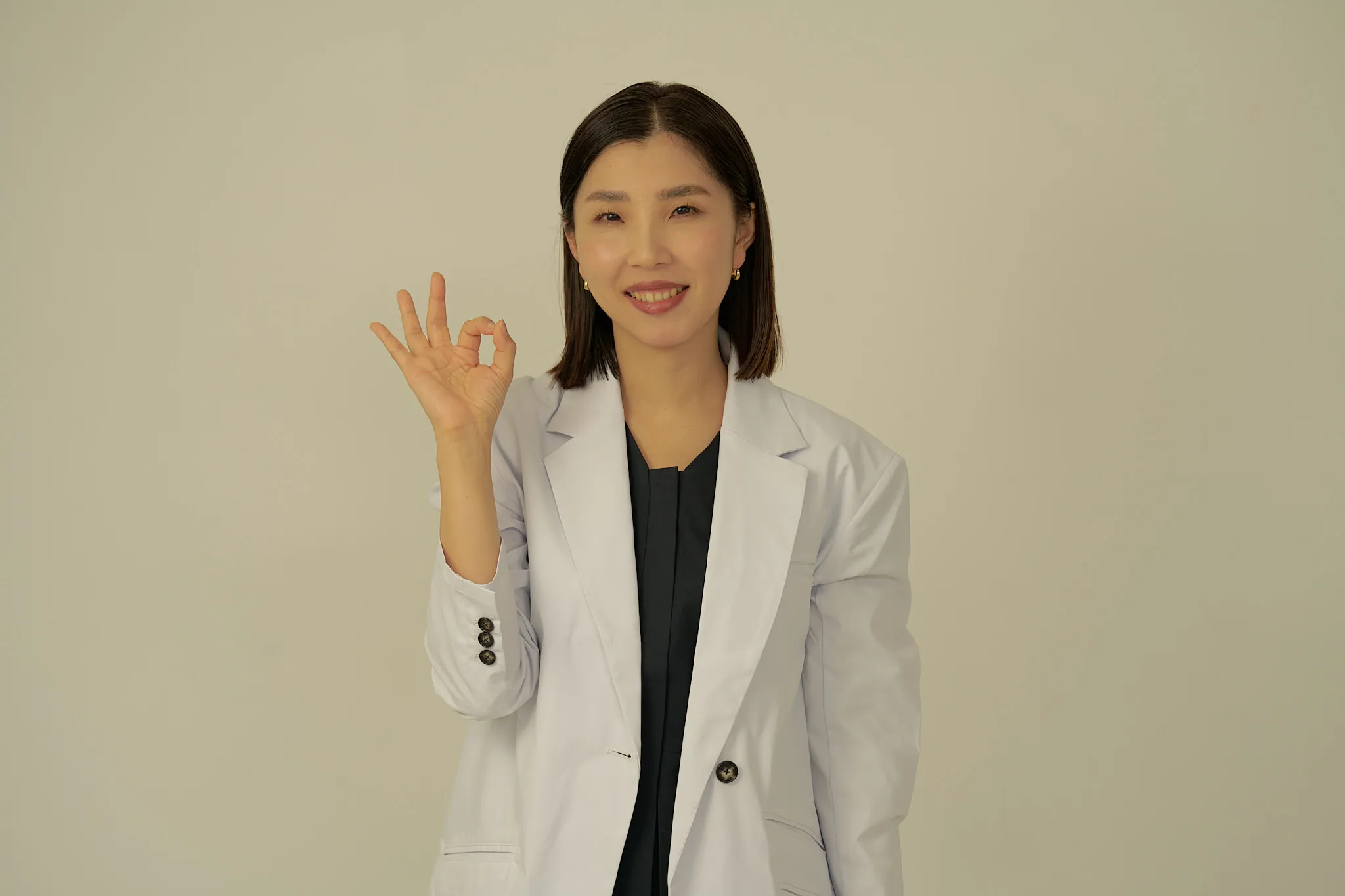
これらの生活改善はすぐに効果が出るものではありませんが、継続することで体質が整い妊娠しやすい土台作りになります。また、これらは妊娠後のママ・パパの健康維持にもそのまま役立つ習慣です。妊活を機に、無理のない範囲で少しずつ生活習慣を見直してみましょう。
4. 必要に応じて妊活検査や専門家の相談を受ける
自宅での取り組みを数ヶ月続けても不安がある場合や、「何か問題がないか確認したい」というときは、産婦人科で妊活相談やブライダルチェック(プレコンセプションチェック)を受けてみるのも良いでしょう。妊活中の基本的な検査としては以下のようなものがあります。
ホルモン検査
女性の生理周期に関わるホルモン値を採血で調べ、排卵がきちんと起きているか、ホルモンバランスに異常がないかを確認します。
卵巣予備能検査(AMH検査)
卵巣内に残っている卵子の数の目安を調べる血液検査です。卵巣年齢とも呼ばれ、年齢に対して卵子の在庫が十分かを見ることができます。妊活の計画を立てる参考になります。
超音波検査
経腟超音波で子宮や卵巣の状態を観察します。子宮筋腫や子宮内膜症、卵巣の嚢胞など妊娠の妨げになり得る疾患の有無をチェックできます。また、排卵前に卵胞の大きさを測定し、排卵日予測に役立てることもできます。
性感染症検査
クラミジア感染などは自覚症状がなくても不妊の原因となることがあります。ブライダルチェックでは梅毒・HIV・クラミジアなどの感染症検査も行います。
精液検査(男性)
男性側の精子の数や運動率・形態などを調べる検査です。これは泌尿器科や不妊外来で受けられます。男性不妊は検査しないとわからない場合が多いので、必要に応じて早めに受けることをおすすめします。
これらの検査を受けておけば、もし異常が見つかっても早期に対策が取れますし、問題なければ安心して妊活を続けられるでしょう。「まだ病院に行くほどではないかな…」と迷う方も多いですが、妊活のための検査・相談は不妊治療専門クリニックだけでなく一般の婦人科でも対応しています。特に35歳以上で妊活を始める場合や、生理不順・月経痛が強いなど気になる症状がある場合は、早めに医療機関で相談してみるとよいでしょう。
妊娠しやすい体づくりのポイント
健康的な生活は妊活の基本です。ここでは妊娠しやすい体」を作るために意識したい5つのポイントを紹介します。男女共通の内容も多いので、ぜひパートナーと一緒に取り組んでみてください。
バランスの良い食事と必要な栄養素の摂取
体は食べ物で作られると言われるように、日々の食事内容が体調や生殖機能にも大きく影響します。栄養バランスの良い食事を心がけ、以下の栄養素を意識して摂りましょう。
葉酸
妊活中・妊娠初期に特に重要なビタミンB群の一種です。ほうれん草、ブロッコリー、レバー、いちご、枝豆などに含まれます。葉酸は胎児の神経管閉鎖障害の予防に役立つため、厚生労働省も妊娠を計画したら1日0.4mgの葉酸サプリメントを摂取することを推奨しています。妊娠前からサプリで補うと安心です。
鉄分
貧血予防と全身の酸素供給に必要です。レバー、赤身の肉、魚介、ほうれん草、ひじき、大豆製品などから摂取できます。女性は月経で鉄が失われがちなので積極的に補給しましょう。
亜鉛
細胞分裂やホルモン代謝に関与し、精子の生成にも重要なミネラルです。牡蠣、牛肉、豚レバー、チーズ、ナッツ類などに含まれます。不足すると精子数の減少や卵巣機能低下につながる恐れがあります。
ビタミンE・ビタミンC
抗酸化作用を持つビタミン類で、生殖細胞の老化防止に役立ちます。ビタミンEはナッツ類、アボカド、うなぎ等に、ビタミンCは柑橘類やキウイ、パプリカ、ブロッコリー等に豊富です。新鮮な野菜果物を毎日摂りましょう。
良質なたんぱく質
ホルモンや卵子・精子の材料となります。肉・魚・卵・大豆製品・乳製品などからバランスよく摂取してください。特に魚介類(青魚)には血行を良くするEPA/DHAも含まれるのでおすすめです。
基本は「主食・主菜・副菜」を揃えた和食中心の食事が理想です。外食やコンビニ食が多い方は、サラダやお惣菜を追加して野菜類を補う、揚げ物ばかり選ばない等、できる範囲で工夫しましょう。またカフェインの過剰摂取は体を冷やすとも言われます。コーヒーや緑茶は1日2~3杯程度に留め、代わりにノンカフェインのお茶や麦茶、ルイボスティーなどに切り替えるのも良いですね。
適度な運動と適正体重の維持
運動不足や極端な肥満・痩せは妊娠率に影響します。適度に体を動かし、適正体重をキープすることを目指しましょう。
適度な運動
全身の血行を良くし基礎代謝を上げるために、週に3日以上、1回30分程度の有酸素運動がおすすめです。ウォーキング、軽いランニング、サイクリング、水泳、ヨガなど、自分が楽しめる運動を取り入れてみてください。運動することでストレス発散にもなり、一石二鳥です。ただし激しすぎる運動(息が上がるようなハードなトレーニング)は逆に体に負担となるので控えめに。「軽く汗ばむくらい」の運動が目安です。
適正体重の維持
女性の場合、痩せすぎると生理不順や排卵障害が起きやすくなり、太りすぎるとホルモンバランスが乱れてこれも排卵障害の原因となります。男性も肥満は精子の質の低下につながる恐れがあります。BMI(体格指数)で18.5未満の痩せすぎ、25以上の肥満に該当する方は、妊活を機に適正範囲まで体重を調整しましょう。急激なダイエットは禁物ですが、栄養バランスを考えた食事と運動でゆるやかにシェイプアップするのが理想的です。
適度な運動習慣と標準的な体重は、妊娠だけでなく将来の生活習慣病予防にも役立ちます。夫婦で一緒に散歩したりジムに通ったりすると継続しやすいので、ぜひ協力してチャレンジしてみましょう。
体を冷やさず血行を良くする
「冷えは妊活の大敵」とよく言われます。冷え性の方は体を温める工夫を取り入れましょう。体温が低いと子宮や卵巣への血流も滞りがちになり、機能低下につながる恐れがあります。
毎日湯船に浸かる
シャワーだけで済まさず、できれば毎日ぬるめのお湯にゆっくり浸かって体の芯から温まりましょう。38~40℃程度のお湯に15~20分ゆったり浸かると血行が促進され、リラックス効果も得られます。湯上がり後は湯冷めしないよう靴下を履くなどしてください。
服装や寝具に配慮
お腹や足元が冷えないよう、冬場は腹巻きやレッグウォーマーを活用したり、夏場でも冷房で体を冷やしすぎない工夫を。就寝時も薄手でもいいので靴下を履く、暖かい素材のパジャマにするなどで冷えを防ぎます。布団や毛布も通気性と保温性の高いものを選ぶと良いでしょう。
体を温める食材を摂る
食事面でも、生姜、ねぎ、にんにく、根菜類、味噌や発酵食品、スパイス類(シナモン等)など体を温める効果があるとされる食材を取り入れてみましょう。逆に生野菜や南国の果物、白砂糖の多いお菓子、冷たい飲み物は体を冷やすと言われますので摂りすぎに注意です。もちろん栄養バランス優先ですが、調理法もサラダよりスープや煮物にするなど工夫できます。
冷え性はすぐには改善しませんが、日々の積み重ねで少しずつ良くなっていきます。体がポカポカして血の巡りが良い状態は子宮や卵巣の働きにもプラスに働きます。男性も同様に下半身を冷やさないようにすると精子の状態改善に役立つ場合があります。お互いに温かい飲み物を淹れ合ったり、冬は湯たんぽを使ったりと、楽しみながら「温活」を心がけてみてください。
禁煙と節酒を心がける
もし喫煙習慣がある場合は、この機会にぜひ禁煙しましょう。タバコに含まれる有害物質は血管を収縮させ血流を悪化させるほか、卵子や精子の染色体にもダメージを与えかねません。喫煙女性はそうでない女性に比べ不妊率が高いとの研究報告もあります。男性も喫煙により精子の数や運動能力の低下が見られることが知られています。将来生まれてくる赤ちゃんのためにも、夫婦で協力して禁煙に取り組みましょう。どうしても難しい場合は禁煙外来の受診も検討してください。
また、お酒もできるだけ控えめにします。適度な飲酒であれば大きな影響はないと言われますが、飲み過ぎは生殖機能に悪影響を与える可能性があります。女性は妊娠が判明した時点で禁酒が推奨されますし、妊活中から習慣的な深酒は避けるようにしましょう。どうしても付き合いやリラックスで飲みたい場合は、週に1~2回、ビールなら中瓶1本程度、日本酒なら1合まで…と上限を決めて節度ある飲酒に留めます。ノンアルコール飲料やソフトドリンクもうまく利用してください。
タバコと過度のアルコールは妊娠率のみならず妊娠後の流産率や赤ちゃんの発育にも影響を及ぼすリスクがあります。「赤ちゃんを迎える準備」と考えて禁煙・節酒にチャレンジしましょう。
ストレスをためず、十分な睡眠をとる
妊活中は何かと神経質になったりプレッシャーを感じたりしやすいものです。しかしストレスはホルモンバランスの大敵。ストレスを感じると脳の視床下部からのホルモン分泌が乱れ、排卵に影響が出る場合があります。また男性もストレスで勃起不全や一時的な精子減少を起こすことがあります。意識的にリラックスする時間を作り、心の健康にも目を向けましょう。
自分なりのリフレッシュ法を見つける
趣味の時間を持つ、軽い運動やストレッチをする、音楽を聞く、アロマを焚く、深呼吸をするなど、どんなことでも構いません。夫婦それぞれがリラックスできる方法を日常に取り入れてみてください。二人で旅行に出かけたりするのも気分転換になります。妊活の話題から少し離れてリフレッシュすることも必要です。
良質な睡眠を確保する
毎日夜更かしが続いたり睡眠不足になると、身体の回復が追いつかずホルモン分泌にも悪影響です。なるべく毎日同じくらいの時間に就寝・起床し、7時間前後の睡眠を目標にしましょう。寝る前にスマホやPCを見ると脳が冴えて眠りを妨げるので、就寝1時間前は画面をオフにして読書やストレッチで過ごすなど工夫すると寝付きが良くなります。深い睡眠は翌日の活力を生み、妊活にも良い循環をもたらします。
周囲のサポートも活用
悩みや不安は一人で抱え込まず、パートナーはもちろん、信頼できる友人や家族に話を聞いてもらうだけでも心が軽くなることがあります。また必要であればカウンセラーや医師に相談することも検討してください。不妊専門クリニックにはカウンセリング体制が整っているところもあります。
心と体は繋がっています。リラックスして穏やかな気持ちで過ごすことが、結果的に妊娠にも良い影響を与えるでしょう。焦りすぎず、かといって抱え込みすぎず、肩の力を抜いて妊活に向き合ってくださいね。
パートナー(男性)ができること
前述のとおり、妊活は決して女性だけのものではありません。パートナーである男性の協力が妊活成功の鍵を握ります。ここでは男性側が妊活中にできる具体的なサポートや取り組みを紹介します。
妊娠に関する理解を深める
まずは男性自身が妊娠・出産について正しい知識を持つことが重要です。女性の体の仕組み(月経周期や排卵のこと、不妊の原因になりうる疾患など)や、年齢による妊娠率の変化、さらに不妊治療の流れなどについて基礎的な情報を共有しましょう。本やインターネットの記事を一緒に読んだり、産婦人科で配布しているパンフレットを参考にするのも良い方法です。知識が増えれば「なぜ今この生活習慣を改善する必要があるのか」「どうしてタイミングをとる日を調整するのか」といった理由も理解でき、妊活へのモチベーションにつながります。
心の支えになり積極的にコミュニケーションを
妊活中、とりわけ治療が必要な状況になると、女性は心身の負担やプレッシャーを感じやすくなります。そんな時、一番の支えになるのはパートナーからの理解と寄り添いです。男性にできることは次のようなことです。
積極的に話を聞く
不安やつらさを感じている様子であれば、まずは耳を傾けてあげましょう。アドバイスよりも「そうか、つらいよね」「頑張ってるの知ってるよ」といった共感の言葉が女性の安心感につながります。妊活について夫婦でオープンに話せる雰囲気を作ってください。
協力的な姿勢を見せる
基礎体温をつけている奥様に「今日は体温どうだった?」と関心を示したり、タイミング法の日程を一緒に考えたり、クリニックの受診にも付き添ったりと、二人三脚で取り組んでいるという姿勢を示しましょう。「任せきり」「他人事」のような態度は厳禁です。小さなことでも協力する姿勢が見えるだけで、女性の心理的負担は大きく軽減します。
ねぎらいと励まし
妊活は短期決戦にならないことも多く、成果が見えずに落ち込む時期もあります。そんな時こそ「いつも頑張ってくれてありがとう」「二人で乗り越えようね」といったねぎらいの言葉や優しいスキンシップで支えてあげてください。夫婦の絆を深める良い機会と捉えて、互いに思いやりを持ったコミュニケーションを意識しましょう。
男性自身の生活習慣改善
体づくりの項目で述べた生活習慣の改善(バランスの良い食事、適度な運動、禁煙、十分な睡眠など)は男性にもそのまま当てはまります。精子の質は生活習慣によって大きく左右されるため、ぜひ夫婦で一緒に取り組んでください。特に次の点は男性側で意識したいポイントです。
禁煙・節酒の徹底
喫煙者の男性は非喫煙者に比べ精子の数・運動率・形態いずれも悪影響が報告されています。タバコは百害あって一利なしと心得て、妊活を機に禁煙しましょう。お酒も控えめに。晩酌が習慣の方は量を減らすかノンアルコール飲料に置き換えるなど工夫してください。
精巣を高温にしない
精子は熱に弱いため、日常で精巣周辺を過度に温めないようにします。長時間のサウナや熱いお風呂に浸かりすぎる習慣は見直しましょう。また締め付けの強い下着やスキニーパンツも通気が悪く温度を上げてしまうので避けた方が良いと言われます。デスクワークで座りっぱなしの方は1時間おきに立ち上がって軽く体を動かすと良いでしょう。
栄養を考えた食事
女性と同様、亜鉛・ビタミンC・ビタミンE・葉酸・たんぱく質など精子に良い栄養素をしっかり摂りましょう。ファストフードや油っこいものばかり避け、野菜・果物・魚もバランスよく。難しければ男性向けマルチビタミンサプリメントなどを活用しても良いでしょう。
適度な運動と十分な睡眠
運動不足の男性はメタボや生活習慣病リスクだけでなく、精子の質低下も懸念されます。無理のない範囲で運動し、体重が多めの方は適正化を目指しましょう。睡眠も大事です。夜更かしせずしっかり寝て、翌日に疲れを持ち越さない生活を。
男性側の体調が整えば精子の状態も改善し、受精の可能性が高まります。妊活は夫婦共同プロジェクトと考え、ぜひパートナーも主体的に取り組んでください。
男性も検査を受け原因を確認する
妊活が一定期間うまくいかない場合、女性だけでなく男性も積極的に不妊検査を受けることが重要です。精液検査は採取した精液を提出するだけの比較的簡単な検査で、男性不妊の有無を調べる第一歩になります。約3割の男性に何らかの精子の問題(精子数減少や運動率低下など)が見つかるとも言われており、男性不妊は症状がなく自覚しにくいのが特徴です。夫婦生活が順調にできていても、実は精子側に原因があったというケースも珍しくありません。
「自分は大丈夫」と決めつけず、ぜひ早めに検査を受けてください。男性不妊の場合でも、原因に応じた治療法(生活習慣の改善はもちろん、薬物療法や手術療法など)がいろいろとあります。男性が積極的に検査・治療に参加することが、結果的に早期の妊娠につながる可能性も高まります。恥ずかしがらず前向きに協力しましょう。
クリニック受診の目安(どのタイミングで相談すべき?)
妊活を始めてしばらく経つと、「そろそろ病院に行くべきか?」と悩む時期が来るかもしれません。一般的に、不妊症の定義は「避妊せず性交渉を続けて1年経っても妊娠しない場合」とされています(日本産科婦人科学会の定義)。したがって、女性がまだ34歳以下であれば1年間は自然妊娠の様子を見ても良いでしょう。ただし、女性が35歳以上の場合はタイムロスを防ぐため半年妊活を続けても妊娠しなければ受診を検討します。さらに女性40歳以上なら3ヶ月試して授からなければ、できるだけ早く検査を受け始めることが推奨されます。
これらはあくまで目安ですが、年齢が上がるほど早めの対応が望ましいことを示しています。「まだ1年経ってないから…」と我慢しているうちに時間だけが過ぎてしまうケースもありますので、不安を感じたら早め早めに専門家に相談することをおすすめします。
また、期間に関わらず以下のような場合も受診を検討しましょう。
生理不順や無排卵月経の疑いがある
生理周期が極端に短い・長い、毎月バラバラ、あるいは基礎体温で排卵の兆候がない場合は、排卵障害の可能性があります。治療で排卵を促す必要があるため早めに受診してください。
月経痛がひどい・月経量が多いなどの症状がある
子宮内膜症や子宮筋腫などの婦人科疾患が隠れていることがあります。これらは不妊の原因にもなり得るため、気になる症状があれば検査しておくと安心です。
過去に性感染症にかかったことがある
特にクラミジア感染症は卵管の癒着を引き起こし不妊原因になることがあります。一度治療済みでも、卵管の通りが悪くなっていないか検査する価値があります。
男性側に気がかりな点がある
精巣の手術歴がある、思春期におたふく風邪で高熱が出た(精巣炎で精子が減るケースがあります)、勃起や射精に困難がある、など男性側に心当たりがある場合も早めに泌尿器科などで相談しましょう。
これらに当てはまらなくても、「半年頑張ったけど不安になってきた」「一度プロに話を聞いてほしい」という場合は受診して構いません。決して大げさなことではなく、妊娠しやすい時期を逃さないための前向きな行動です。
産婦人科や不妊外来では、まず基本的な検査を行ってご夫婦の現在の状態を評価します。原因が判明すればそれに応じた治療を計画できますし、特に問題が見つからなければひとまず妊活継続で経過を見るという選択もあります。「何も分からないまま不安な状態」でいるより、検査をして現状を把握することは大きな安心につながります。お二人にとって最善のタイミングで受診を検討しましょう。
レディースクリニックなみなみでできるサポート
当院レディースクリニックなみなみは、妊活中の皆さまを専門的かつ親身にサポートする婦人科クリニックです。「女性の人生の波(なみ)に寄り添うかかりつけ医」として、妊娠を望む段階から妊娠・出産、更年期までトータルに診療しております。妊活に関して当院で提供できる主なサポート内容を紹介します。
妊活相談(不妊症相談)
妊活を始めたばかりの方、なかなか妊娠できず不安な方向けに、医師による相談外来を行っています。基礎体温表の見方やタイミング法のアドバイス、生活習慣の指導など、お一人おひとりの状況に合わせて丁寧にご説明します。「何から始めていいかわからない」という段階でもお気軽にご相談ください。専門医があなたの妊活計画を一緒に考えます。
プレコンセプションチェック(ブライダルチェック)
妊娠前の包括的な健康チェックを実施しています。基本的な血液検査に加え、ホルモン値測定、卵巣機能の指標となるAMH検査、感染症検査(風疹抗体や性感染症の有無)などを一度に調べることが可能です。東京都の助成事業の対象にもなっており、条件を満たせば費用補助を受けることもできます。妊娠に向けて不安要素を事前にクリアにし、必要な予防接種や治療につなげることができます。
不妊症の初期検査・治療
なかなか妊娠しない場合の基本的な不妊検査を女性・男性ともにサポートします。女性の排卵有無確認、子宮卵管エコー検査(卵管の通りを超音波で確認する検査)なども可能です。男性の精液検査についても、提携機関と連携してスムーズに受けられるよう案内いたします。検査結果に応じて、タイミング法の指導や排卵誘発剤の処方など一般不妊治療の初期段階を当院で行うことができます。
必要に応じ専門クリニックと連携
当院は「不妊専門クリニックの前に相談できる身近な婦人科」として位置づけています。体外受精など高度な治療が必要と判断される場合には、信頼できる不妊専門施設へ速やかにご紹介することが可能です。院長自身、不妊治療にも長年携わってきた産婦人科専門医ですので、適切なタイミングで適切な医療につなげるよう責任をもってサポートいたします。もちろん、ご紹介後も妊娠判定や妊娠後の健診などで当院に通いやすい環境を整えています。
まとめ
妊活は、赤ちゃんを授かるために夫婦で取り組む大切なプロセスです。妊娠しやすい体づくりやタイミングの工夫など、できることはたくさんありますが、何よりお二人が協力し合い前向きな気持ちで続けることが成功への鍵となります。思うように結果が出ず不安になる時もあるかもしれません。しかしその際は一人で抱え込まず、パートナーや専門家に頼ってください。最近では多くのカップルが不妊の悩みに向き合い、適切な治療で乗り越えていらっしゃいます。
レディースクリニックなみなみでは、妊活中の方々が安心して相談できる場を提供し、専門的な知見からサポートいたします。「ベビーを迎えたい」という願いに寄り添い、一緒に歩んでいきますので、いつでも頼ってくださいね。皆さまの妊活が実を結び、笑顔で新しい命を迎えられる日が来ることを心より願っています。焦らず一歩ずつ、あなたのペースで進んでいきましょう。私たちも全力でバックアップいたします。どうか頑張りすぎず、頑張ってください。応援しています。
妊活のポイント
妊活を始めたら早めに生活習慣を整え、排卵日を意識したタイミング法を試しましょう。一定期間妊娠しなければ検査を受け、必要なら不妊治療にステップアップすることも検討します。年齢要因も踏まえて「時機を逃さない」ことが大切です。また、妊活は夫婦の共同作業です。辛い時こそ支え合い、コミュニケーションを密にしてくださいね。
妊活に関するよくある質問
どのくらい妊活しても妊娠しない場合に不妊症と考えるべきですか?
一般的には1年間妊活(避妊せず定期的に性交渉)を行っても妊娠しない場合、不妊症の可能性があるとされています。ただし女性の年齢が35歳以上の場合は6ヶ月、40歳以上では3ヶ月妊娠しなければ受診を検討することが推奨されています。多くのカップルは85%以上が1年以内に妊娠すると言われますので、1年以上授からない場合は検査を受けて原因を調べた方がよいでしょう。早めの対応が後々の近道になります。
生理不順でも自然妊娠できますか?
生理不順の程度によります。たまに数日のズレがある程度なら心配ありませんが、周期がバラバラで排卵日が特定できない場合や無月経の期間がある場合は排卵障害の可能性があります。排卵が起こっていなければ自然妊娠は難しいため、婦人科でホルモン検査を受け、必要なら排卵誘発などの治療を行うことになります。ただ、生理不順でも治療によって排卵を促せば妊娠できるケースは多いので、まずはきちんと検査・治療を受けることをおすすめします。
妊活中、葉酸サプリは摂った方が良いですか?
はい。葉酸サプリメントは妊活中から積極的に摂取することが勧められています。葉酸は胎児の神経管閉鎖障害(先天異常)のリスクを下げる栄養素で、妊娠初期に必要量が求められます。そのため妊娠が判明してからでは遅く、妊娠を希望する時点でサプリメントでの葉酸補給を開始するのが望ましいのです。厚生労働省も1日あたり400マイクログラム(0.4mg)の葉酸をサプリ等で摂るよう推奨しています。もちろん普段の食事からも葉酸を多く含む緑黄色野菜や果物を摂取しましょうが、必要量を食事だけで満たすのは難しいためサプリで補ってください。
妊活には男性側の検査や治療も必要ですか?
必要に応じて行うことを強くおすすめします。不妊の原因の約半分は男性側にもありますので、女性だけでなく男性も自分の問題として捉えることが重要です。具体的には、精液検査によって精子の状態を確認するのが第一歩です。これは痛みもなく短時間で終わる検査ですので、妊活を半年~1年続けて妊娠しない場合や、女性側に原因が見当たらない場合は男性もぜひ検査を受けましょう。万一異常が見つかっても、多くは生活習慣の改善や薬物療法、必要に応じて外科的治療で改善を試みることができます。また、男性が治療に協力的であることは女性の精神的支えにもなります。夫婦一緒に検査・治療に向き合うことが妊活成功の近道です。

執筆者兼監修者プロフィール
東大産婦人科に入局後、長野県立こども病院、虎の門病院、関東労災病院、東京警察病院、東京都立豊島病院、東大病院など複数の病院勤務を経てレディースクリニックなみなみ院長に就任。
資格
- 医学博士
- 日本産科婦人科学会 産婦人科専門医
- FMF認定超音波医
…続きを見る


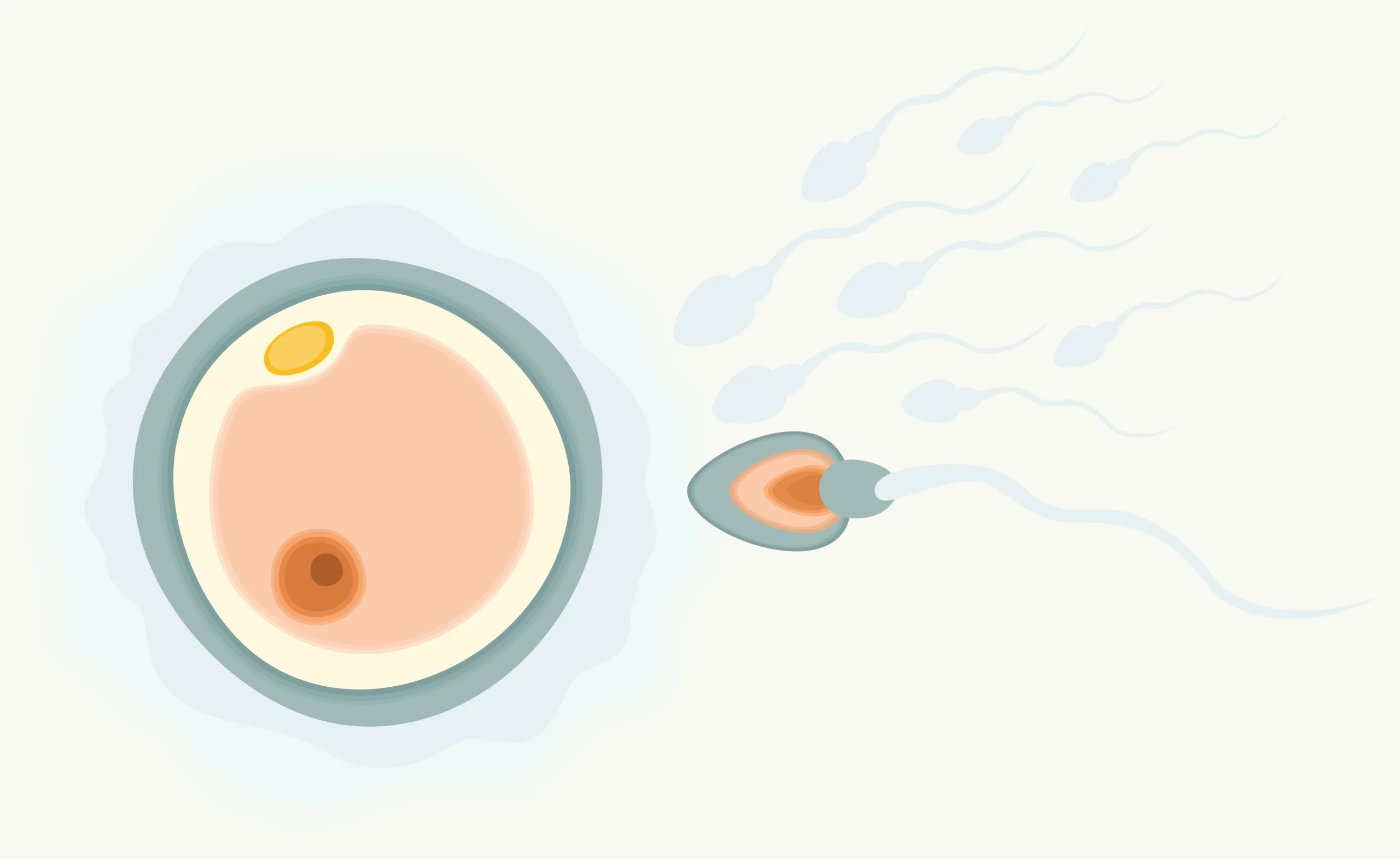











早く始めなきゃ」と一人で焦る必要はありませんが、将来的に子どもを望むのであれば “できるだけ若いうちに” 取り組み始める方が有利なのは確かです。夫婦でしっかり話し合い、タイミングを見計らって妊活の第一歩を踏み出しましょう。